
「介護福祉士試験でノーマライゼーションが良く出るって聞いたんですけど、試験に必要な内容と、覚え方について教えてください」
「ノーマライゼーションは頻出のところになりますね。ですから、確実に得点したいところです。必要な内容をまとめていきますね」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護福祉士試験で必要なノーマライゼーションの内容と覚え方について解説します
こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上携わり、現在は初任者研修や実務者研修、介護福祉士の試験対策講座などを担当しています。
さて、介護福祉士試験に比較的よく出る問題として、ノーマライゼーションに関するものがあります。
ノーマライゼーションとは、誰もが当たり前に生活できる社会、環境を作らなければならない、という考え方です。
介護福祉士試験に向けて覚えておく必要があるのは、バンク–ミケルセン、ニィリエ、ヴォルフェンスベルガー、そして糸賀一雄の4人とその功績です。
というわけで、今回は介護福祉士試験で得点するために、ノーマライゼーションに関連するおさえるべきポイントについて解説します。
ノーマライゼーションってなに?
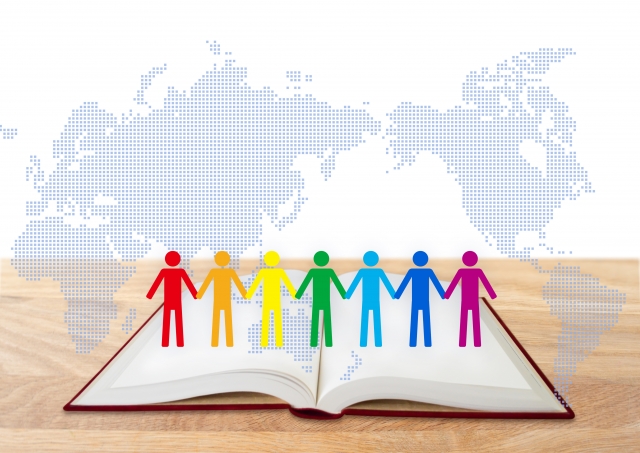
普段の生活の中で、ノーマライゼーションという言葉を耳にしたり、使うことはないでしょう。
ですから、少しとっつきにくく感じるかもしれません。
では、「ノーマル」はどうですか。特に珍しい言葉ではありませんよね。ノーマライゼーションの元の言葉は、「ノーマル」(普通)です。
そして、これが動詞になると「ノーマライズ」(普通にする)となります。
さらに、「ノーマライズ」を名詞形にすると、「ノーマライゼーション」(普通化)となります。
ノーマライゼーションとは、障害があってもなかっても、どんな人でも当たり前に生活できるよう、社会、環境を「普通化」しましょう、という意味になります。
ノーマライゼーションで覚えるべき人物とその功績

「ノーマライゼーションの意味がわかったところで、この考え方を提唱し、世に広めた人物をおさえておきましょう。ノーマライゼーションに関連して覚えておくべき人は、主に3名です。名前とともに、どこの人か、そして、大づかみでいいので功績について覚えておいてください」
「3人を覚えておけばいいですね!それならなんとかなりそう。」

おさえるべき3人
- ニルス・エリク・バンク–ミケルセン(デンマーク):提唱者「ノーマライゼーションの生みの父」
- ベンクト・ニィリエ(スウェーデン):広めた人「ノーマライゼーションの育ての父」
- ヴォルフェンスベルガー(アメリカ):発展型「ソーシャルロール・バロリゼーション」
ニルス・エリク・バンク–ミケルセン
ノーマライゼーションの提唱者で「ノーマライゼーションの生みの父」が、デンマークのニルス・エリク・バンク–ミケルセンです。
1950年代、デンマークでは知的障がい者は施設に収容され、そこで生涯を過ごす、つまり知的障がい者の隔離が行われていました。
隔離施設では、知的障がい者はおおよそ人間らしい生活からかけ離れた、非常に劣悪な生活を強いられました。
ナチスの収容所に収監された経験のあるバンク–ミケルセンは、知的障がい者の隔離施設での生活を「まるでナチスの収容所のようだ」と嘆いたのです。
そして、バンク–ミケルセンと同様、環境の改善を望む知的障がい者の親の会と活動を共にし、行政に働きかけました。
そこで提出した要請書のタイトルに「ノーマライゼーション」が使われ、1959年、ノーマライゼーション法とも呼ばれる知的障害者福祉法が誕生したのです。
ノーマライゼーションという言葉が、法律に用いられたもっとも古いケースになります。
そして、ノーマライゼーションの提唱者であるバンク–ミケルセンは「ノーマライゼーションの生みの父」と呼ばれるようになりました。
ベンクト・ニィリエ
バンク–ミケルセンが提唱したノーマライゼーションを、国際的に広めたのがスウェーデンのベンクト・ニィリエです。
スウェーデン知的障害児者連盟に所属していたニィリエは、ミケルセンのノーマライゼーションに影響を受け「知的障害者は、ノーマルなリズムにしたがって生活し、 ノーマルな成長段階を経て、 一般の人々と同等のノーマルなライフサイクルを送る権利がある」としました。
そして、ノーマライゼーションを8つの原理にまとめました。
8つの原理
- 知的障害のみならずあらゆる障害のある人々がノーマルな1日を体験する権利がある。
- ノーマルな1週間のリズムを体験する権利がある。
- ノーマルな1年間のリズムを体験する権利がある。
- 子どもから大人になっていくという、ノーマルなライフサイクルを体験する権利がある。
- 自己決定権と、個人としてノーマルに尊厳を受ける権利がある。
- その人の住む社会の文化習慣に則ってノーマルな性的生活をする権利がある。
- その国におけるノーマルな経済的生活水準を得る権利がある。
- その人の住む社会におけるノーマルな住居・環境水準を得る権利がある。
これらを成文化し、世界に広めた功績から、ニィリエは「ノーマライゼーションの育ての親」と呼ばれています。
ヴォルフ・ヴォルフェンスベルガー
アメリカに広がったノーマライゼーションを、独自の理論で発展させたのが、アメリカのヴォルフ・ヴォルフェンスベルガーです。
ヴォルフェンスベルガーは、ノーマライゼーションに代わる新しい理念として、「ソーシャルロール・バロリゼーション」を提唱しました。
ソーシャルロール・バロリゼーションとは、社会的役割の実践という意味で、これまで低い役割が与えられてきた障がい者に対して、高い社会的役割を与え、それを維持するように能力を高めるよう促すことで、障がい者の社会的環境を改善しようというものです。
ヴォルフェンスベルガーは、社会が障がい者を「価値の低い人」として位置付けていることを問題視し、障がい者の社会的地位の価値をいかに高めていくか、そして、そのために障がい者個人の能力をいかに高めていくかを重視しました。
日本でのノーマライゼーション、人物と功績

「次に、日本においてノーマライゼーションの考え方を広めた人物、そしてその人物の功績について見ておきましょう。おさえておくべき人物は1人です」
「1人ですか、よかった!これ以上増えたら頭がパンクしてしまいます」

糸賀一雄

日本においてノーマライゼーションの考え方を広めたのが、糸賀一雄(いとがかずお)です。
糸賀は、1946年、知的障がい児の教育を行う近江学園を設立、さらに1963年にびわこ学園を設立しました。
「恩恵的に与える福祉ではなく、当事者こそが社会を変革していく主体であり、その実現を目指したいとなみこそが福祉である」という思想を持ち、重症心身障害児への取り組みを通して、「どんな人も同じ発達の道筋を辿る」、そのことを社会的に認め合い、支え合っていくという意味で「発達保障」を提唱、さらに、どのような障害があっても社会の中で受け止められるべきであるとして、地域福祉活動の重要性を主張しました。
「この子らに世の光を」という哀れみではなく、障がい児は輝ける素材であり、磨きをかけて輝かし「この子らを世の光に」という言葉を残しています。
これらの功績から、「社会福祉の父」と呼ばれています。
【介護福祉士】ノーマライゼーションの覚え方:まとめ

「ノーマライゼーションで絶対におさえておかないといけないのは3人、プラス1人、とその功績です。これまでの出題傾向だと、ここをおさえておくことで確実に得点できます。必須で覚えておくべきところを下にまとめておきますね」
「人の名前、国、功績、しっかりとおぼえます!」

必須内容
- バンク–ミケルセン:デンマーク、提唱者、「ノーマライゼーションの生みの父」
- ニィリエ:スウェーデン、ノーマライゼーションの8つの原理をまとめる、「ノーマライゼーションの育ての父」
- ヴォルフェンスベルガー:アメリカ、ソーシャルロール・バロリゼーションを提唱
- 糸賀一雄:近江学園、びわこ学園設立、「この子らを世の光に」、「社会福祉の父」
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
