
「介護職がサービスを提供する中であうハラスメントには、どのようなものがありますか?あわないために、また解決するためにどのような対策が必要ですか?」
「最近は、ハラスメントに関する意識が社会的に高まってきていますね。介護職は、仕事の特性上、ハラスメントにあいやすい仕事と言えます。ですから、対策をしっかりと講じなければなりませんね」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護職がサービスを提供する中で、利用者や家族から受けるハラスメントの内容や対策について書いています
こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上従事しており、複数の介護施設の施設長などを経験してきました。
現在は介護のコンサルタントとしても、施設に関わって仕事をしています。
さて、以前より介護人材の不足が叫ばれています。そんな中で、不足をさらに助長しかねない問題として、利用者やその家族から受けるハラスメントがあります。
国は、令和3年度から、介護事業所へのハラスメント対策に必要な措置を義務付けており、ハラスメントによる離職を防止しようとしています。
では、実際に介護の現場ではどのようなハラスメントが起こっているのでしょうか、そして、どうすれば防ぐことができるでしょうか。
今回は、介護現場で介護職が受けるハラスメントの原因や種類、内容、そして 対策について解説します。
介護職が利用者、家族から受けるハラスメントと対策について

では、介護職が利用者やその家族から受けるハラスメントについて見ていきましょう。
まずは、介護職がハラスメントを受ける原因について整理していきます。
そして、次に介護職が受けやすいハラスメントの種類や内容、さらには、介護職だからハラスメントの問題が起こりやすい、という問題点にも切り込んでいきたいと思います。
介護職が受けるでハラスメントの原因
介護職が利用者や家族からハラスメントを受ける原因としては、次のようなことがあげられます。
ハラスメントの原因
- 介護職という仕事の特殊性
- 認知症という病気
- 身体的、精神的な苦しみによるストレス
- ハラスメントへの意識の低さ
- 介護職特有のハラスメントに対する意識
介護職という仕事の特殊性
介護の仕事は、身体を近づけたり、密着させて行う場面の多い仕事です。また、利用者と2人っきりになることも少なくありません。
このような状況が、ハラスメントを引き起こす原因のひとつとなっているでしょう。
認知症という病気
認知症という病気も、ハラスメントの原因のひとつです。
認知症は、正しく認知できない病気です。ですから、介護職の介護に対して、利用者が暴言や暴力によって介護を拒否することが あります。
認知症の利用者は、自分の置かれている状況や、介護しようとしている介護職を正しく認知できず「知らない人間が自分に不利益になることをしようとしている」と感じて、暴言や暴力で介護に抵抗することで、自分を守ろうとするのです。
他にも、認知症によって理性のコントロールが難しくなり、セクシャル・ハラスメントに至る人もいます。
原因が病気ですから、まずは介護職としての専門性を発揮し、認知症の方が穏やかに介護を受けられるようにする必要があります。
たとえば、非言語コミュニケーション、表情や態度、しぐさ、それに準言語コミュニケーション、口調や声のトーンといったものを見直すことです。
穏やかな表情で、安心感のある口調で話しをすることによって、利用者が介護を受け入れやすくするのです。
ただし、解決しない場合は、医療的な対応が必要になることもあります。
上司に相談したり、ケアカンファレンスで解決に向けて話し合う場を持つなどしてください。
身体的、精神的な苦しみによるストレス
介護が必要な利用者は、身体になんらかの障害を抱えていたり、思うように動かせなかったり、といった状況に置かれています。
他にも、病気による慢性的な痛みに苦しんでいることがあります。。
思うようにならない身体、生活といったことが精神的な負担となり、イライラ、不安、など精神的に不安定な状態になります。
また、家族にとっても、日々の介護は心身ともに負担となります。
そのような、持って行き場のない怒りや不安などの苦しみが、介護職に対するハラスメントとの原因になるのです。
ハラスメントへの意識の低さ
ハラスメントに対する意識が高まったのは、近年になってからです。
利用者が仕事をしていた年代、たとえば、昭和の初期〜中期あたりでは、ハラスメントに対する意識は今と比べものにならないぐらい低いものでした。
仕事上での上司からのパワハラ、セクハラが、今のように問題になることはほとんどありませんでした。
そのような認識の低さが、ハラスメントの原因のひとつになっていると言えるでしょう。
介護職特有のハラスメントに対する意識
介護職の仕事に対する認識、意識が、ハラスメントを防止、対策への障害になることがあります。
たとえば、介護職の専門性においては、認知症の方が暴言や暴力を振るうのには原因や理由がある、と捉えます。
また、セクシャル・ハラスメントについても、利用者が触ってきそうと思ったら、触られないような立ち位置を取ったり、相手の手を自然に取って、触らせないようにするといったのも技術と教えられることがあります。
決して間違いではないのですが、そのように考えすぎると、暴言や暴力、セクシャル・ハラスメントが発生するのは、自分の技術や知識が未熟だから、となってしまいます。
その結果、ハラスメントをする利用者や家族に対して「嫌と言えない」であったり、会社の上司や先輩に相談できない状況が起こりやすくなります。
介護職が受けるハラスメントの種類や内容
次に、介護職が受けるハラスメントの種類と内容について見ていきましょう。
ハラスメントの種類
- 身体的な暴力
- 精神的な暴力
- 性的な嫌がらせ(セクシャル・ハラスメント)
身体的な暴力
介護職を叩く、殴る、つねる、爪で引っ掻く、他にも噛み付く、髪の毛を引っ張るといった行為があげられます。
高齢者だから、叩かれてもそれほど痛くないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
痛いですし、爪で引っ掻かれたりすると傷が残ることもあります。
髪の毛を引っ張られて、たくさん抜けてしまったり、といったことも起こります。
ただし、一方的に介護職が被害者か、というとそうでもなくて、介護拒否をしている認知症の利用者に強引に介護をしようとした結果、利用者が興奮してきつい暴力に発展する、という傾向があります。
精神的な暴力
暴言や威圧的な態度が、精神的な暴力になります。
利用者が介護を拒否する際に、大声をあげたり、殴るふりをして威嚇するといった行動です。
また、家族からも、暴言を吐かれることがあります。
さらに、本来介護保険ではできないサービスを、威圧的な態度や暴言によって強制されるといったことがあります。
具体的には、利用者にしかしてはいけない家事支援や、ケアプランに入っていないサービスを強制される、といったことです。
性的な嫌がらせ(セクシャル・ハラスメント)
不必要に身体に触れてきたり、触る必要のないところを触ったり、性的な話しや発言を繰り返すといったことがあります。
俗に言うセクシャル・ハラスメントです。
介護の仕事は、身体を近づけたり、密着させる場面の多い仕事です。
ですから、セクハラは発生しやすく、避けようにも避けられない場面も少なくありません。
たとえば、車椅子からベッドへ移乗(移す)の介護をしている最中は、触られたくないところを触られても、身体を離すことができません。
転倒事故を起こしてしまうからです。
身体に触る、性的な発言をする以外にも、性的なビデオをわざと見たり、そのようなビデオを介護職が見えるところに置いておくなどといったことがあります。
セクシャル・ハラスメントは、男性利用者から女性介護職に対して多く発生しますが、男性介護職が被害にあうこともあります。
また、男性介護職が、女性利用者からセクシャル・ハラスメントで訴えられるといったケースも、稀にあります。
実際にあったケースとしては、恋心を抱いた女性利用者に対して、男性介護職が丁重に交際を断ったところ、腹いせにセクシャル・ハラスメントをされたと訴えられるといったことがありました。
介護職のハラスメントへの対策とは?
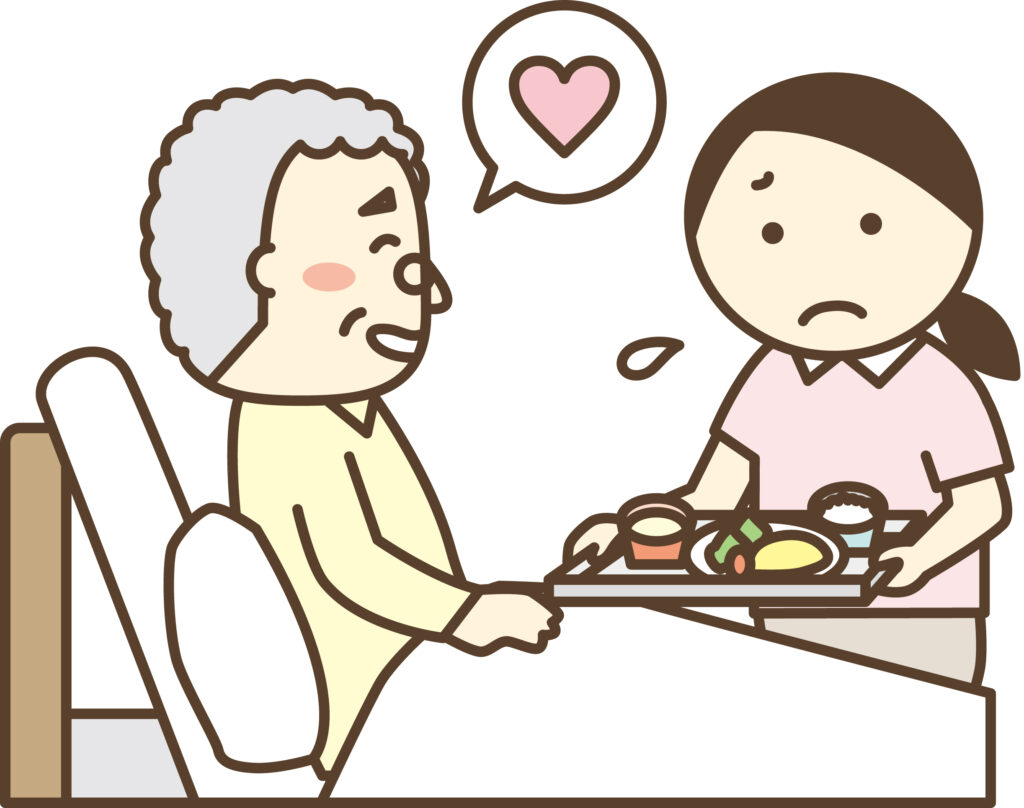

「介護の仕事をする上で、ある程度のハラスメントは仕方ないんですかね。でも、やっぱりハラスメント受けるのは嫌です。なにか対策はありませんか?」
「介護の人材不足という点でも、ハラスメントは大きな問題です。国も、介護職に対するハラスメントを深刻にとらえ、施設や事業所に対してハラスメント対策を義務付けています。ですから、我慢しないで相談することが大切ですね」

我慢をせずに相談する
利用者や家族からハラスメントを受けたら、自分で抱え込まずに上司や先輩に相談してください。
抱え込んでしまうと、精神的な負担が大きくなり、介護の仕事を続けられなくなるからです。
現在は、ハラスメントに対して社会的に意識が高くなってきています。
国も、介護の事業所にハラスメント対策を義務付けています。ですから、きちんとした事業所であれば、適切に対応してくれるはずです。
専門職としての知識、技術の見直し
とはいえ、介護職という仕事上、一般的なハラスメントがすべて当てはまるわけではありません。
たとえば、認知症の方であれば、ハラスメントを起こす原因は病気です。認知症ケアは介護職の専門分野なので、病気の特性を知って、適切な介護を提供していかなければなりません。
つまり、ハラスメントにならないような知識や技術を持ちながら、介護を実施することが求められるということです。
しかし、経験が浅いうちは、どこまでが専門職として求められるのか、判断がつかないでしょう。
そこで悩まないためにも、前述したように上司や先輩に相談するようにしてください。
きちんとした判断や、なにかしらの助言がもらえるはずですし、時には利用者への関わりを避けてもらえるなど、対策を講じてくれるでしょう。
繰り返しになりますが、くれぐれも一人で抱え込まないようにしてください。
介護職が利用者、家族から受けるハラスメントと対策について:まとめ

「ハラスメントは、とにかく自分で抱え込まないで相談すること、ですね!」
「そうですね。ハラスメントは、受けた人がどう思うか、が重要ですから、自分の気持ちをきちんと伝えることが大切です。みんなが我慢してるから、であきらめるのではなく、必ず相談してください」

この記事のまとめ
- 介護職は、利用者との距離が近かったり、1対1でサービスを提供する、専門性を考えると訴えにくい、などから、ハラスメントが起こりやすいと言える
- ハラスメントの内容は、身体的な暴力、精神的な暴力、性的な嫌がらせ
- 自分で抱え込まないで、必ず事業所の上司や先輩に相談する
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
