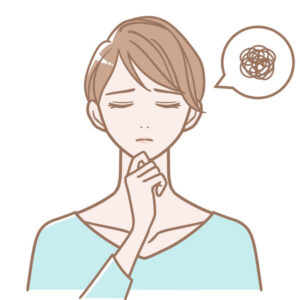
「介護職をしているのですが、妊娠しました。生活があるので、出産ぎりぎりまで、そして、子供が生まれた後も正社員として介護の仕事を続けたいと思うんですけど、なんだか会社からも、同僚や上司からもいてほしくないような雰囲気があって。だから、制度の利用も気を使うし、将来性も見えなくなってきました。やっぱり、正社員としてバリバリ働きながら子供を持つって、女性には難しいんですかね」
「いや、それはマタニティハラスメントに該当しますよ。今の時代は、女性が働きながら子供を持てる職場の環境づくりが事業主に求められています。そして、実際に働きながら出産、育児ができるように、体制を整えていかなければなりません。そうでないと、違法になることもあります。まずはどのようなことがマタニティハラスメントに該当するのか、そして、解決するためにどのような方法があるのかを見ていきましょう」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護現場でのマタニティハラスメントの内容や対処方法について書いています
こんにちは、せいじです。
介護業界に20年以上携わり、施設長として様々なハラスメント対策を講じてきました。
その経験の中には、予防策、そして実際に起きたハラスメントへの対策があります。
さて、介護職が退職する理由のひとつとして、マタニティハラスメントがあります。
マタニティハラスメントとは、妊娠、出産、育児等を契機に、休業制度などを利用させなかったり、嫌味を言ったり、嫌がらせをするといったことを指します。
現在は、事業主によるマタニティハラスメントが法律で禁じられているのに加え、上司、同僚からのマタニティハラスメントを防止する義務が事業主に課せられています。
といわけで、今回は介護職が介護現場で受けることがあるマタニティハラスメントの内容や、対処方法について解説します。
マタニティハラスメントとは?

では、まずはマタニティハラスメントの定義について見ていきましょう。
法律では、マタニティハラスメントを次のように定義づけています。
マタニティハラスメントの定義
職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること
男女雇用機会均等法第11条の2
労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること
育児・介護休業法第10条
これらの定義により、どのような内容がマタニティハラスメントにあたるのかを見ていきましょう。
マタニティハラスメントにあたる内容
マタニティハラスメントとは、妊娠、出産、育児に関することで、労働者の就業環境が害される、つまり仕事がしにくくなったりすることなどを言います。
具体的には、次のようなものがあげられます。
マタニティハラスメントの内容
- 妊娠などを理由に解雇したり、有期雇用者の契約を更新しない
- 契約内容を強制的に変更する
- 不利益な配置転換
- 減給や降格、昇進、昇格しにくくする
- 不利益な自宅待機を命じる
- 心ない発言
- 配慮のない行動
マタニティハラスメントの種類
マタニティハラスメントには、次のような種類に分けることができます。
マタニティハラスメントの種類
- 制度等の利用への嫌がらせ型
- 状態への嫌がらせ型
それぞれ掘り下げて行きます。
制度等の利用への嫌がらせ型
制度等の利用への嫌がらせ型とは、妊娠、出産、育児などに関係する制度を利用する、もしくは利用しようとすることに対して、前述したハラスメントにあたる言動が行われることを言います。
たとえば、軽度な業務に従事する環境に変更してもらった場合などに「妊婦だから仕事をしない」といった発言をされたり、育児休暇を取得しようとすると、減給や降格、また、昇進に影響するとか、取得できないように圧をかけられるといったことです。
状態への嫌がらせ型
状態への嫌がらせ型とは、妊娠により、それまでのように就業できなくなった状態に対して、前述のような内容のハラスメントを行うことを言います。
「もう自分ひとりの身体じゃないんだから、無理して仕事をするべきじゃない!という発言についても、相手を思いやってのことであるにせよ、しつこく繰り返し、妊娠している職員が働きにくさを感じるのであれば、マタハラになる可能性があります」

介護現場でのマタハラの具体例


「このようなことをマタニティハラスメントって言うんですね。私も介護現場で経験しています。私だけじゃなく、私の友人や同僚も、私と同じような経験があるって話しをしていました。具体的に言うと・・・」
介護の現場で実際にあったマタニティハラスメントとしては、次のようなものがあります。
実際にあったマタハラ
- 「妊娠したら、仕事をせずに済むからいいねぇ」
- 「みんなが頑張ってるのに、よく残業せずに帰れるね」
- 「みんなのおかげで育児休暇取れるのわかってる?」
- 「あなたが育休を取っていると、新しい人を雇うことができないから、戻ってくるのか来ないのか、はっきりしてほしい」
- 「これからも妊娠や子育てがあるなら、重要なポストにつけることはできないね」
- 「どうしてこんな忙しいときに子供作ったの」
- 「他にも妊娠してる人いるんだから、今は子供作らないでね」
- 産休を取ろうとすると、嫌な顔をされるから取れない
- 産休を認めてもらえない
- 切迫早産の診断書を出したら、とても嫌な顔をされた
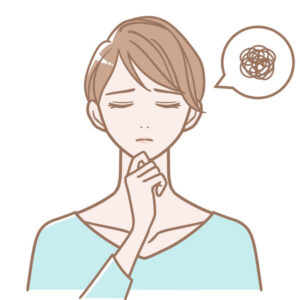
「妊娠って、見た目の変化はわかっても、中身の辛さってわからないじゃないですか。ホルモンのバランスが変わったりして、体調も変化してしまうし、つわりがひどくなることもあるし、でもそれってなかなか見えませんよね。わかってもらえない辛さがあります。まるでサボってるみたいに見られる辛さ。
妊娠経験のある先輩方も、「私の時代はこんなに大変だった!でもがんばった!」ていう目線でしか見てくれないので、誰にもわかってもらえません・・・」
マタハラへの対処方法

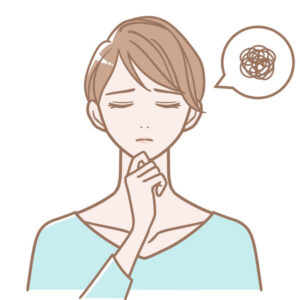
「このまま仕事を続けたら、悪影響が出そうで怖いです。でも、お金は必要だし、これからも仕事がしたいし。何か解決する方法はないんでしょうか」
「マタハラを受けた場合は、然るべきところに相談するようにしてください。セクハラやパワハラもそうですが、ひとりで抱え込まないことが重要です。妊娠して、今までみたいに働けないことで、事業所や他のスタッフに迷惑をかけていると後ろめたさを感じる必要はありません。事業所としてあるべき姿は、妊娠している中でも働ける環境にすることですから」

施設、事業所の相談窓口に相談する
マタハラを受けたら、ひとりで抱え込まないで相談することが重要です。
まずは、施設、事業所に設置されている相談窓口の担当者に相談するようにしてください。
ただし、事業主がハラスメントを防止することを義務化しているとはいえ、組織の仕組みとして機能していないところもあります。
相談しても解決する見込みがないのであれば、施設、事業所以外の機関へ相談するようにしてください。
その他の相談窓口に相談する
会社以外のマタニティハラスメントの相談機関としては、次のようなところが挙げられます。
マタハラの相談窓口
- 総合労働相談コーナー
- 都道府県労働局雇用均等室
- 女性の人権ホットライン
総合労働相談コーナー
厚生労働省が設置している、職場のトラブルの総合相談窓口です。
各都道府県に窓口を設け、無料、予約不要で相談を受け付けています、
都道府県労働局雇用均等室
各都道府県の労働局に設置されている相談窓口です。
マタニティハラスメントなどの相談に応じてくれる他、内容に応じて施設や事業所に行政指導を行なったり、紛争解決援助を実施します。
女性の人権ホットライン
法務省が設置している、女性の人権の問題に関する電話での相談窓口です。
また、電話だけでなく、インターネットで相談することも可能です。
相談は無料で、もちろん秘密厳守で対応してくれます。
介護現場で起こるマタハラとは?内容や対処方法を解説します:まとめ

「相談できるところがあると思うと、ちょっと心が楽になりました。妊娠してても安心して働ける職場環境って大切ですね。自分が妊娠して、改めてこんなことが気になるんだ、こんな気持ちになるんだというのがわかりました。今後、妊娠などがある同僚がいたら、私のできることをしていきたいと思います」
「目に見えない、直接感じることができないからこそ、相手を慮っていく必要がありますね。これは、介護にも通ずる話しですよね。なお、マタニティハラスメントをなくしていくためには、事業主や施設の管理者といった上層部の働きが欠かせません。ハラスメントについての勉強をし、起こらない組織づくりをしていく必要がありますね」

この記事のまとめ
- マタニティハラスメントは、妊娠、出産、育児に関係して、会社や上司、同僚から不利益を受けること
- マタハラを受けたら、会社の相談窓口やそれ以外の窓口に相談する
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
