
「介護福祉士試験に向けて勉強しているんですが、まずは人間の尊厳と自立から取り掛かろうと思います。問題の傾向や対策を教えてください」
「人間の尊厳と自立では、利用者主体、利用者本意、自己決定、がキーワードになってきます。また、人権などに関係する人物や制度の名前を覚えておく必要がありますね」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護福祉士試験の試験科目である、「人間の尊厳と自立」について、出題の傾向やおさえておくべきポイントについて書いています
こんにちは、せいじです。
介護業界に20年以上携わり、現在は介護の講師として、介護福祉士筆記試験対策講座などを複数の学校で担当しています。
さて、この記事では、介護福祉士試験の科目のひとつである「人間の尊厳と自立」について、出題傾向や試験対策をまとめていきます。
ぜひご覧ください。
「人間の尊厳と自立」はどんな科目?

人間の尊厳と自立は、介護をする上で必要な基本の考え方、理念になります。
ここでは、その理念の理解と、現代社会に至るまでに、どのような人物が、どのような貢献をしたのか、そして、どのような制度が作られててきたのか、について学ぶ科目となります。
介護福祉士として支援をするにあたっては「誰しもが個人として尊重され、自分らしく生きる権利がある」ということをベースに持っておく必要があります。
そして、この理念が今日のように謳われるようなった歴史を知ることで、理念の重要性を理解します。
キーワードとして、「自立」「自律」「自己決定」「自立支援」「利用者の主体性」といった基本原理があります。
この言葉が持つ意味をしっかりとおさえていきましょう。
出題基準
公益財団法人社会福祉振興・試験センターには、出題基準が以下のように示されています。
| 大項目 | 中項目 | 小項目(例示) |
|---|---|---|
| 1 人間の尊厳と人権・福祉理念 | 1)人間の尊厳と利用者主体 | ・人間の多面的理解 ・人間の尊厳 ・利用者主体の考え方、利用者主体の実現 |
| 2)人権・福祉の理念 | ・人権思想・福祉理念の歴史的変遷 ・人権尊重 | |
| 3)ノーマライゼーション | ・ノーマライゼーションの考え方、ノーマライゼーションの実現 | |
| 4)QOL | ・QOLの考え方 | |
| 2 自律の概念 | 1)自立の概念 | ・自立の考え方 |
| 2)尊厳の保持と自立 | ・自己決定.自己選択 ・意思決定 ・権利擁護.アドボカシー |
出題数
人間の尊厳と自立の科目では、毎年2問出題されます。
ただし、介護福祉士としてのベースになる考え方、そして制度などが範囲になるため、他の科目でも取り上げられることが少なくありません。
ちなみに、介護福祉士試験では、1科目でも0点であれば、全体の点数が合格基準を超えていても不合格となります。
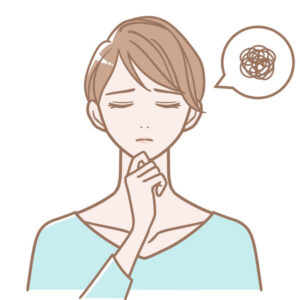
「てことは、2問のうち1問は正解しないと、他でどれだけ得点できても不合格になるってことですよね・・・そんなの無理ですよ・・・」

「よくそう早とちりする方がいるんですが、そうではないんです。人間の尊厳と自立は、介護の基本の10問と合わせて、合計12問のうち1問正解でOKになります」

「あっ、そうなんですね!12問のうち1問でも正解すればいいってことなら、なんとかなりそうです!」
「人間の尊厳と自立」の出題傾向は?


「ところで、「人間の尊厳と自立」の科目では、具体的にどんな問題が出るんでしょうか?」
「この科目では、出題のパターンがはっきりとしています。1問は事例問題で、読解力があれば答えられます。そして、もう1問は知識の問題になりますが、年によっては非常に難問の場合があります。事例問題を確実に落とさないようにすることが重要ですね」

「人間の尊厳と自立」の出題傾向
人間の尊厳と自立の出題傾向をまとめると、次のようになります。
出題傾向
- 人間の尊厳と自立に関係した人物や用語、法律などの知識を問う問題
- 事例から、適切な対応を選択する問題
人間の尊厳と自立の攻略方法
人間の尊厳と自立に関係した人物や用語、法律などの知識を問う問題では、幅広い知識が求められます。
介護に関係した知識だけではなく、一般常識も含めたところになってくるので、非常に難解な場合があります。
ズバリの解答ができるように準備するのは難しいので、消去法で答えられるレベルに持っていきましょう。
事例では、「自立」「自律」「自己決定」「自立支援」「利用者の主体性」といった基本原理に基づいた選択肢を選ぶことでクリアできます。
利用者本人に注目して解答しましょう。
過去問題対策
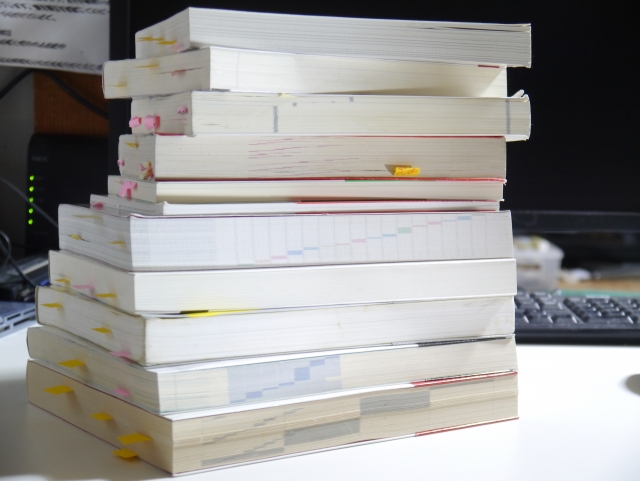
ここからは、過去問題で傾向を確認していきましょう。
第34回「人間の尊厳と自立」問題
問題
著書『ケアの本質-生きることの意味』の中で,「一人の人格をケアする とは,最も深い意味で,その人が成長すること,自己実現することをたすけることである」と述べた人物として,正しいものを 1 つ選びなさい。
1 神谷美恵子
2 糸賀一雄
3 フローレンス・ナイチンゲール(Nightingale, F.)
4 ミルトン・メイヤロフ(Mayeroff, M.)
5 ベンクト・ニィリエ(Nirje, B.)
解説
1 神谷恵美子
ハンセン病療養所の国立療養所長島愛生園の精神科医長として勤務。ハンセン病患者の精神医学調査をもとに、「生きがいについて」を出版
2 糸賀一雄
社会福祉の父と呼ばれ、知的障がい児の教育を行う近江学園を設立。「この子らを世の光にー近江学園二十年の願い」を出版。
3 フローレンス・ナイチンゲール
「近代看護教育の母」と呼ばれる。クリミア戦争で負傷した兵たちへの献身的な看護や、医療衛生改革を実施。
4 ミルトン・メイヤロフ
正解
5 ベンクト・ニィリエ
「ノーマライゼーションの育ての親」と呼ばれる。ノーマライゼーションを8つの理念にまとめ、国際的に広めた。
問題
Aさん(80 歳,女性,要介護 1 )は,筋力や理解力の低下がみられ,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。訪問介護員(ホームヘルパー)がいない時間帯は,同居している長男(53 歳,無職)に頼って生活をしている。長男はAさんの年金で生計を立てていて,ほとんど外出しないで家にいる。
ある時,Aさんは訪問介護員(ホームヘルパー)に,「長男は暴力がひどくてね。この間も殴られて,とても怖かった。長男には言わないでね。あとで何をされるかわからないから」と話した。訪問介護員(ホームヘルパー)は,Aさんのからだに複数のあざがあることを確認した。
訪問介護員(ホームヘルパー)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
1 長男の虐待を疑い,上司に報告し,市町村に通報する。
2 長男の仕事が見つかるようにハローワークを紹介する。
3 Aさんの気持ちを大切にして何もしない。
4 すぐに長男を別室に呼び,事実を確認する。
5 長男の暴力に気づいたかを近所の人に確認する。
解説
今回の問題は、人権擁護に関する問題でした。
ここでは、高齢者虐待防止法を把握しておく必要があります。
高齢者虐待防止法には、介護職員に通報義務を課しています。
虐待を発見したら、市町村に通報しなければならない、という義務です。
この義務については、秘密保持義務よりも優先されるとなっています。
ですから、正解は1となります。
第33回「人間の尊厳と自立」問題
問題
人権や福祉の考え方に影響を与えた人物に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 リッチモンド(Richmond,M,)は、『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』をまとめ、現在の社会福祉、介護福祉に影響を及ぼした。
2 フロイト(Freus,S,)がまとめた『種の起源』の考え方は、後の『優生思想』につながった。
3 マルサス(Malthus,T,)は、人間の無意識の研究を行なって、『精神分析学入門』をまとめた。
4 ヘレン・ケラー(Keller,H,)は、『看護覚え書』の中で「療養上の世話」を看護の役割として示した。
5 ダーウィン(Daarwin,C,)は、『人口論』の中で貧困原因を個人の人格の問題とした。
解説
1 リッチモンド
正解
2 フロイト
人間の無意識の研究を行なって、『精神分析入門』をまとめた。
3 マルサス
『人口論』の中で貧困原因を個人の人格の問題とした。
4 ヘレン・ケラー
設問の内容は、フローレンス・ナイチンゲールのもの。
5ダーウィン
『種の起源』の考え方は、後の『優生思想』につながった
問題
自宅で生活しているAさん(87歳,男性,要介護 3 )は, 7 年前に脳梗塞(cerebral infarction) で左片麻痺となり,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用していた。Aさんは食べることを楽しみにしていたが,最近,食事中にむせることが多くなり,誤嚥を繰り返していた。誤嚥による緊急搬送の後,医師は妻に,「今後も自宅で生活を続けるならば,胃ろうを勧める」と話した。妻は仕方がないと諦めていたが,別に暮らしている長男は胃ろうの造設について納得していなかった。長男が実家を訪れるたびに,Aさんの今後の生活をめぐって口論が繰り返されていた。妻は訪問介護 員(ホームヘルパー)にどうしたらよいか相談した。
介護福祉職の職業倫理に基づく対応として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1 「医療的なことについては発言できません」
2 「医師の判断なら,それに従うのが良いと思います」
3 「Aさん自身は,どのようにお考えなのでしょうか」
4 「息子さんの気持ちより,一緒に暮らす奥さんの気持ちが優先されますよ」
5 「息子さんと一緒に,医師の話を聞きに行ってみてください」
解説
「自己決定」「利用者の主体性」を考える問題です。
選択肢の中で、本人であるAさんの自己決定について考えているのは、選択肢3だけです。
ですから、正解は3になります。
まとめ
問題を解いていくためには、次のような法令をおさえておく必要があります。
覚えておきたい法令等
- 世界人権宣言第22条
- 日本国憲法第13条、第25条
- 社会福祉法第3条
- 老人福祉法第2条
- 障害者基本法
- 介護保険法
- 障害者総合支援法
- 障害者差別解消法
- 高齢者虐待防止法
- 障害者虐待防止法
- エンパワメント、アドボカシーといった権利擁護の理解
- 自立と自律の理解
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
