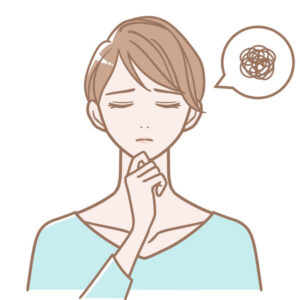
「この前、先輩が燃え尽き症候群になって、介護職を辞めてしまったんです。いつも利用者さんに向き合って熱心に介護をされていたので、私もとてもショックでした。どうして燃え尽き症候群になるんですか?また、防ぐ方法ってないんでしょうか」
「それは残念でしたね。燃え尽き症候群は、まじめで熱心な人ほどなりやすいという特徴があります。良い介護職がなりやすいと言えますね。そんな人が辞めてしまうのは、介護業界にとっても損失ですよね。原因や症状、対策について見ていきましょう」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護職の燃え尽き症候群(バーンアウト)の原因や症状、対策について解説しています
こんにちは、せいじです。
介護の仕事を20年以上しており、現在は介護の研修の講師やコンサルタントの仕事をしています。
さて、燃え尽き症候群(バーンアウト)というものをご存知でしょうか。
一生懸命仕事をしていた人が、急にやる気を失って仕事をやめてしまう、その姿がまるで燃え尽きたように見えることから、燃え尽き症候群という名前が用いられています。
介護職は、他の仕事くらべて燃え尽き症候群が起こりやすいとされています。
利用者に感情移入し、なんとか元気になってもらいたい、その一方で、人間の身体は年齢を重ねることによって衰えていきます。
せっかく頑張って介護をしても、利用者が徐々に悪くなっていく現実を見て、燃え尽き症候群になってしまいやすいのです。
つまり、真面目で仕事に熱意を持っている人ほどなりやすいということですね。
こんな優秀な職員を失うわけですから、施設や事業所にとってはつらい話しです。
というわけで、今回は介護職の燃え尽き症候群について解説します。
燃え尽き症候群(バーンアウト)ってなに?

では、燃え尽き症候群について見ていきましょう。
燃え尽き症候群とは、それまで熱心にがんばってた人が、突然やる気を失ってしまう症状を言います。
モチベーション高く一生懸命にやってきたのに、それに見合う結果が出なかったり、逆に、目標を達成してしまうことで、打ち込めるものを失うのです。
介護職でいうと、利用者のことを考え、自立支援に向けて日々頑張っている中で、その成果が全然出なかったり、また、利用者さんが突然亡くなってしまったり、といったときに起こります。
他にも介護福祉士の試験に向けて頑張っていたのが、取得することで目標を失ってしまうといったことが引き金になります。
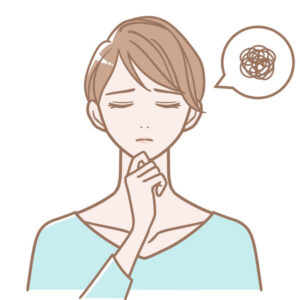
「どれだけ頑張っても成果が出ない、目の前の大切な人が悪くなっていくのを見ていると、自分のやっていることが虚しくなってきたり、無力感を抱いてしまうでしょうね」
燃え尽き症候群(バーンアウト)の症状
次に、燃え尽き症候群の具体的な症状について見ていきましょう。燃え尽き症候群には、次のような症状があります。
燃え尽き症候群の症状
- やる気がおこらない
- 朝起きることができない
- お酒の量が増える
- 人との関わりを避けるようになる
- 会社に行きたくなくなる
「まるでうつ病のような症状ですが、実際に医学的には、燃え尽き症候群はうつ病の一種とされています」

介護職が燃え尽き症候群になりやすい理由
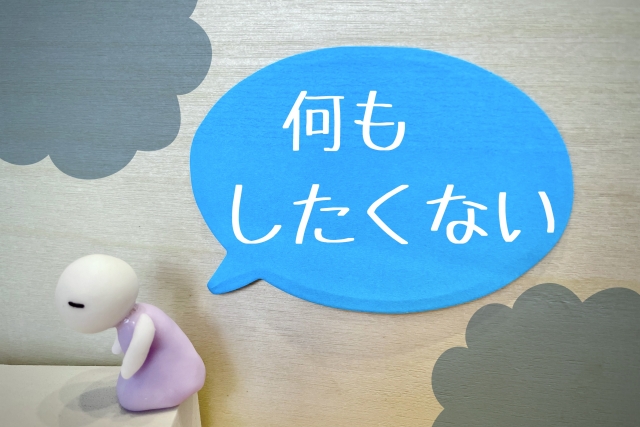
ところで、介護職は燃え尽き症候群を起こしやすい仕事とされています。その理由にはどんなことがあげられるでしょうか。
まとめると次のようになります。
燃え尽き症候群になりやすい理由
- 利用者の支援にのめり込みやすい
- 目に見えて成果が出にくい
- ストレスを抱えやすい
掘り下げていきます。
利用者の支援にのめり込みやすい
介護職の仕事は、利用者の日常生活を支援する仕事です。
支援する中で、利用者に感情移入してしまい、没頭してしまうことがあります。
なんとか少しでも良くなってもらいたい、という思いが強くなりすぎるからですね。
中には、自分のプライベートの時間も使って利用者の支援を考えてしまう人もいます。
目に見えて成果が出にくい
そうやって熱心に支援をしても、高齢者介護はなかなか成果が出にくい仕事です。
なぜなら、人間は年齢を重ねることによって身体能力が低下していくからです。
これは、生きとし生けるもの、避けることができません。
ですから、どれだけ自立に向けて支援をしても、利用者が良くなっていかない、ということが起こるのです。
それでも頑張り過ぎてしまうと、やがて自分のやっていることに自信が持てなくなって燃え尽きてしまうということが起こりやすいんですね。
ストレスを抱えやすい
燃え尽き症候群の原因としては、ストレスが関係しています。
ストレスが溜まることによって、燃え尽き症候群になるリスクが上がるからです。
介護職はストレスの多い仕事とされています。
ですから、うまくストレスマネジメントができないと、燃え尽き症候群を起こしやすくなるんですね。
介護職の燃え尽き症候群(バーンアウト)対策とは

ここからは、燃え尽き症候群にならないように、対策を見ていきましょう。
まとめると、次のような方法があります。
燃え尽き症候群への対策
- しっかりと睡眠をとる
- ストレスをマネジメントする
- 自分自身でなんとかなる目標を決める
掘り下げていきます。
しっかりと睡眠をとる
ストレスと睡眠不足は関連性があります。睡眠不足が続くとストレスが溜まりやすくなるからです。
なので、しっかりと睡眠をとるようにし、ストレスを解消していきましょう。
そうすることで、燃え尽き症候群になるリスクを減らすことができます。
「忙しい人はつい睡眠時間を削ってしまいがちですが、睡眠不足はストレス以外にも、パフォーマンスを低下させる原因になったり、心身ともに健康を損なうリスクを高めます。良い仕事をしようと思ったら、睡眠時間を削るのではなく、しっかりと確保することが重要なんですね」

ストレスをマネジメントする
前述した睡眠不足もそうですが、他にもストレスを抱えた際に、それを解消できる方法を持っておくことが重要です。
ストレスを管理し、うまく自分で解消していくのです。これをストレスマネジメントと言います。
適切にストレスを解消することができれば、燃え尽き症候群だけでなく、心身ともに負担を減らすことができます。
-

介護職はストレスマネジメントが超重要!理由やその方法とは
こんな悩みを解決します こんにちは、せいじです。 介護の仕事を20年以上しており、現在は介護の研修の講師やコンサルタントの仕事をしています。 さて、介護職は大きなストレスがかかる仕事だと言われています ...
続きを見る
自分自身でなんとかなる目標を決める
燃え尽き症候群の原因のひとつは、自分がいくら頑張っても求める成果が得られないことによるものです。
ですから、自分でどうにかなる目標を持っておくと、燃え尽き症候群になることを防ぐことができます。
前述したように、介護では利用者の成果を目標にしてしまうと、なかなかうまくいかないことが多いです。
本当であれば、利用者が悪くなっていかないことも立派な介護の成果なのですが、没頭しすぎるとそこに目が行かなくなります。
そうであれば、自分自身で完結できる目標に目を向け、実施していくほうが精神衛生上も良いでしょう。
ただし、大きな目標をひとつだけ掲げてしまうと、達成した時に燃え尽きてしまうことがあります。
逆に、大き過ぎていつまで経っても達成ができず、それによって燃え尽きてしまうこともあります。
ですから、大きな目標に到達するために、過程の小さな目標を設定し計画的に進んでいきましょう。
そうすれば、ひとつをクリアしたからといって燃え尽きてしまうことを防ぐことができます。
介護職が燃え尽き症候群(バーンアウト)になりやすい理由とは?:まとめ

「燃え尽き症候群は、きちんと対策を講じれば避けることができそうですね。のめり込むぐらい大好きな仕事ですから、そういった人には長くやってもらいたいですものね」
「そうですね。過度なストレスが原因なので、うまくコントロールする術を身につけることが重要ですね」

この記事のまとめ
- 燃え尽き症候群は、まじめで熱心な人がなりやすい
- うつ病のような症状が出て、介護への意欲を失ってしまい、退職につながる
- 原因はストレスなので、ストレスマネジメントを身につけて、ストレスをコントロールすることが重要
ということで、今回はこのへんで終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

