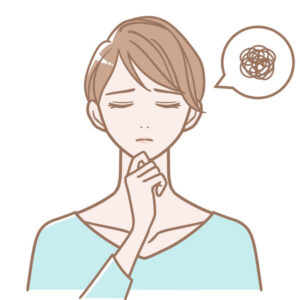
「あぁ〜、介護の仕事に初めて就いたんですけど、なかなか仕事が覚えられないんですよ・・・。先輩方は励ましてくれるんですけど、覚えられない自分が嫌になりそうです」
「介護の仕事は覚えなければならないことが多いですからね。効率よく覚えていきたいですね。今回はその方法について紹介していきましょうか」

この記事の内容
この記事の内容
介護の仕事がなかなか覚えられなくて、ほとほと困っている、というのを解決する方法について書いています
こんにちは、せいじです。
介護業界に20年以上携わり、現在は初任者研修や実務者研修といった、介護職になるための、そしてキャリアアップするための研修の講師をしています。
さて、介護の仕事を始めたけれど、仕事がなかなか覚えられなくて悩んでいる、という人も多いのではないでしょうか。
どんな仕事でもそうですが、介護の仕事は特に最初に覚えないといけないことが満載なんですよね。
利用者の名前と顔、そして介護をする上での注意点や留意点、業務の流れや内容、そして介護の知識、技術、さらにはいっしょに働くスタッフのことや会社のことなど、これらを覚えないと、1人の介護職としてうまく動けるようにはなりません。
覚えが悪いと、他のスタッフの足を引っ張ってしまうし、利用者にも迷惑をかけてしまう、そう考えると、なんで自分はこんなに覚えが悪いんだろう、と嫌になってしまうこともあるかもしれません。
1日でも早く覚えて、覚えられないストレスから解放されましょう。
というわけで、今回はなかなか介護の仕事を覚えられない人の解決策について書いていきます。
なかなか介護の仕事を覚えられない人の解決策とは

では、介護の仕事を覚えられない人への解決策を見ていきましょう。
とはいえ、楽をして一足飛びに覚えられるようになる裏技的な方法はありません。
基本的なことを実践していくしかないんですよね。
ですが、基本的なことの中身を深めていくことで、効率よく覚えることができるようになります。
まとめると、次のようになります。
効率よく仕事を覚える方法
- メモ帳を活用する
- 聞きたいことを明確にして聞く
- 仮説を立てて聞く
それぞれ掘り下げていきます。
メモ帳を活用する
仕事を覚える上で、基本かつ必要不可欠なこととして「メモを取る」があげられます。
そして、早く仕事を覚えるためにも、メモは欠かせません。
私も新人の頃は、上司から「メモ魔たれ」(鬼のようにメモを取る人になれ、という意味)と指導されたことを思い出します。
ただし、メモもただ単に書き留めておくだけでは役に立ちません。
メモには次の二つの目的を持って取る必要があります。
メモを取る目的
- 書くことで覚える
- 見返して活用する
ひとつは、書くことで記憶に残りやすくする目的です。
書くと覚えやすくなるのは、アウトプットすることになるからです。
人は、アウトプットすることで、記憶に残りやすくなるのです。
そして、メモの目的の2つ目は、書き留めた内容を実際に活かすことです。
業務を遂行する中で、忘れていることを見返して仕事に活かせるメモにしなければならない、ということです。
そのためには、書き留めた情報を後で整理するようにしてください。
1日の仕事が終わったあとにまとめておきましょう。
そうすることで、さらにアウトプットする機会となり、困ったときにすぐに必要な情報が取り出せるメモとなります。
まとめ方としては、次のような形がおすすめです。
メモのまとめ方
- 利用者の情報を整理する
- 業務の流れを整理する
- 指導された内容を整理する
ここは、もう少し掘り下げておきます。
利用者の情報を整理する
介護の仕事をするためには、最初に利用者の名前を覚える必要があります。
名前と顔が一致しないと、介護ができないからです。
さらに、利用者の特徴や介助する際の留意点もおさえていかなければなりません。
たとえば、〇〇さんの食事は刻み食を提供する、とか、水分にはトロミをつける、といった情報ですね。
利用者の情報をまとめる例としては、次のような形があります。
利用者の情報のまとめ方
- 居室表
- 座席表(食事形態、トロミの有無)
- 利用者別情報ページ
施設で介護職をしているのであれば、居室表を作っておきましょう。
どの利用者がどこの部屋なのかを把握しておくことで、仕事がやりやすくなるからです。
次に、食堂の座席表を作ります。利用者の食堂での席は基本的に決まっています。
ですから、食堂の図を描き、利用者の席を書いていくことで、誰がどこに座っているか把握しやすくなります。
そして、その図に食事形態(刻み食、ペースト食など)や、トロミの必要性を書いておくと、配膳時や水分を準備する際に薬に立ちます。
また、利用者ごとに1ページ設け、利用者の情報をまとめておきましょう。フェイスシートやアセスメントシートから情報を吸い上げ、その情報を活用しつつコミュニケーションをとり、そこで得た情報を付け加えていきます。
情報が増えるほど、利用者の顔と名前が一致し、理解が深まっていきます。
業務の流れを整理する
教わった業務をメモとして残し、あとで整理しておきましょう。
たとえば、ごみの出し方、浴室のセッティング、後片付け、洗濯の仕方や衣類の取り扱いなどをまとめておけば、メモを見ながら実施することができます。
浴室の準備も、自分ががっつり入浴介助をするようになれば、どこになにが必要かを自然に覚えることができますが、指示を受けながらしている間は、なかなか必要性を自然に把握することができません。
ですから、図として、かごをどこに配置するのか、お湯の設定方法は?といったことを残しておくと、いちいち聞かなくてもメモを見るだけで実施できるようになります。
逆に言うと、なぜその位置にカゴを置くのか、といった根拠を合わせて押さえておくことで、覚えやすくなります。
指導された内容を書き留める
あとは、都度先輩から指導された内容をまとめておきましょう。
リアルタイムでは、とりあえず文字に残すだけで精一杯になりますよね。
ですから、仕事が終わってから、思い出しながらまとめていきます。まとめることで、しっかりとアウトプットできますから、記憶に残りやすくなります。
この際に、誰からの指導内容かも明記しておくと、覚えやすくなります。指導されたときの場面を思い出しやすくなるからです。
映像として場面を覚えておくことで、記憶しやすくなります。
聞きたいことを明確にして聞く
メモを活用して、一度言われたことを確実に実施できるように努め、先輩の手を煩わせないように努力するしても、先輩に聞かなければならないことも出てきます。
そんなときは、質問する前に「なにを聞きたいのか」を明確にし、相手に伝わるように考えてから聞くようにしてください。
聞かれた相手は、なにを聞きたいのかがわからないと、答えようがないからです。
ちんぷんかんぷんの質問をされた相手は、自分の時間を無駄にされたと感じるでしょう。
そうなると、あなたの評価は下がってしまいます。
考えられた質問であれば、そのような事態を避けることができます。
そして、ただ聞くだけでなく、自分で考えた上で聞いたほうが、聞いた内容を記憶しやすくなります。
仮説を立てて聞く
さらにもう一歩進めるのであれば、質問をする前に仮説を立ててから聞くようにしてください。
自分なりに考えた上でひとつの結論をもち、「〇〇でいいですか?」とその仮説の結論を確認する形で先輩に聞くのです。
より自分で考えている形になるため、記憶に残りやすくなりますし、先輩の印象としても、丸投げの質問より、本人が考えた上での質問なので、自発性を感じてもらえる効果があります。
なかなか介護の仕事を覚えられない人の解決策とは:まとめ

「ただ単にメモを取るだけじゃなくて、工夫しながら、考えながら取ることが大切なんですね!」
「そうですね。それに、メモを見ながら仕事をしているだけでは、実はいつまで経っても覚えられなかったりします。メモに頼ってしまって、記憶しようとしないからです。ですから、基本的にはメモを見ないで実施して、困ったら見るようにした方がいいですね」

この記事のまとめ
- メモを取り、業務後にまとめる(アウトプットで覚えやすく!)
- 先輩に聞く際は、質問の意図、内容を明確にしてから行う
- 一歩進んで、自分ありの仮説を立ててから聞くとより覚えやすい
ということで、今回はこのへんで終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
