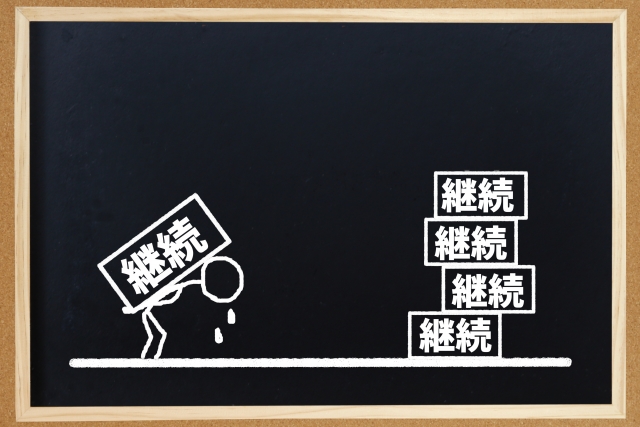「介護職って、退職者が多いって言われるじゃないですか。長く続く人の特徴ってどんなものがあるんですか。また、長く続けるために必要なことってありますか?」
「介護職としてせっかく仕事を始めても、1週間も経たずに辞めてしまう人も少なくないですね。でも、その中でも10年、20年と続けている人もたくさんおられます。そんな人の特徴や、長く続けるために必要なことについて、今日はまとめていきましょう」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護職を長く続けられる人の特徴や、長く続ける方法について書いています
こんにちは、せいじです。
介護の業界に20年以上携わり、10年ほどの間は、施設長などの管理職を経験しました。
現在は、介護の研修の講師やコンサルタントの仕事をしています。
さて、介護の仕事は退職者、離職者が多い職種です。
介護の仕事をはじめてみたものの、続けられずにやめていく人が少なからずいるんですね。
いっぽうで、介護の仕事を何十年も続けている方もおられます。その違いはどういったことでしょうか。
続けられる人の特徴をまとめると、次のようになります。
介護職を続けられる人の特徴
- 人間関係の構築が得意
- ストレスを溜め込まない
というわけで、今回は介護の仕事が続けられる人の特徴と、続けるために必要なことについて解説します。
介護職が長く続く人の特徴とは?

では、介護の仕事が長く続く人の特徴について見ていきましょう。
人間関係の構築が得意な人
介護職の退職理由第1位は、人間関係の問題によるものとなっています。
介護職同士の人間関係がうまく構築できず、退職に至るケースが多いんですね。
つまり、介護職は、職員同士の関係を構築するのが、他の仕事よりも難しい職種だということになります。
その理由としては、多様な価値観、年齢層の人が集まって働く職場だからというのがあげられます。
介護の仕事は、他の仕事から転職して就く人が非常に多いという特徴があります。
転職してくる人が多いということは、それぞれ異なる仕事で培った、仕事に対するベースを持って働くことになります。
ですから、仕事に対する価値観のちがいによって、考えの食いちがいが起こりやすいと言えます。
また、転職者が多いということは、上司と部下の年齢が逆転してしまう状態が発生しやすくなります。
高校や専門学校、大学から新卒で介護の仕事をはじめる人がいるいっぽうで、30〜50代で転職してはじめるという人も多くいて、スタートの年代が多様なんですね。
そんな中で、高校を出てすぐはじめた人は、20代後半で10年ぐらいのキャリアを重ねていて、管理者やリーダーといった役職に就いていたり、少なくとも指導的な立場になっていたりします。
新しく入ってくる転職組は、多くが年上の人になるわけです。
年上に指導をしないといけない、もしくは年下から指導を受けないといけない、そんな状況が発生しやすいことが、人間関係の問題が多くなる1つの原因になっているのでしょう。
そんな状態でも、うまく人とコミュニケーションをはかり、人間関係を作ることができると、深刻な問題にならずに介護職を続けやすくなります。
ストレスを溜め込まない人
介護の仕事は、前述した人間関係の問題に代表されるように、精神的な負担の大きい仕事です。
ですから、ストレスを溜め込まないようにする必要があります。
つまり、ストレス耐性が高い人や、ストレスを発散することがうまい人が、介護の仕事を続けやすくなります。
介護の仕事を長く続ける方法

ここからは、介護の仕事を長く続ける方法について見ていきましょう。
長く続ける方法をまとめると、次のようになります。
介護の仕事を長く続ける方法
- 相談できる相手を見つける
- 乗り越えた先のことを考える
- 職場はそこだけではないと割り切る
- 自分に向いているサービス形態を見つける
- 派遣で実際に働いてから職場を決める
掘り下げていきます。
相談できる相手を見つける
介護の仕事を続けていくためのひとつ目のコツは、相談できる人を作ることです。
人に相談することで、悩みを客観的に考えられるようになるからです。
人に悩みを相談すると、心や頭の中にある問題を外に出すことができます。
外に出すことができると、頭の中で悶々と考えているよりも、客観的に考えることができるんですね。
客観的に考えられるようになると、問題の解決策も見つけやすくなります。
ですから、人に相談することが、悩みの解決につながり、仕事を続けやすくなるのです。
相談できる相手が職場で持てると、続けられる可能性はグッと上がるでしょう。
乗り越えた先のことを考える
辛い状況を乗り越えるコツとして、乗り越えた後のことを考えるという方法があります。
乗り越えた時に、どれだけ自分にメリットがあるかを考えることで、前向きになれたり、ストレス耐性が高まったりする効果があるからです。
たとえば、3年介護の仕事を続ければ、介護福祉士の受験資格が手に入ります。
介護福祉士の資格を取れば、資格手当てが増えたり、転職先の選択肢が増えたりします。
待遇面や環境面で、自分が求める職場を選びやすくなるんですね。
このように、今の苦労が次につながることが明確にわかれば、耐えることも可能になるかもしれません。
職場はその施設だけではないと割り切る
とはいえ、どうしても我慢できない状況も起こりえるでしょう。
それに、我慢しすぎて、精神的な健康を損なってしまっては元も子もありません。
そんな時は「職場はここだけではない、他にもたくさんある」と割り切ることも必要です。
割り切りをすることで、自分が追い詰められてしまうのを防ぐことができるからです。
追い詰められると、人間は思考する力や判断力が低下してしまいます。
ですから、必要以上に深刻に考えてしまう、といったことが起こりやすくなるんですね。
そのような状態を防ぎ、冷静に考えることができると、視野を広く持つことができます。
実際、介護の仕事はどこも人不足です。
求人の多い業界なので、選択肢はたくさんあります。
無理してそこで続けなくてもいいのです。
そう考えると、視野が広がり、今の環境を改善する方法が見えてきたりします。
結果、逆にその職場で仕事が続けられることもあるんですね。
自分に向いているサービス形態を見つける
介護職は、サービス形態によりいろいろな働き方があります。
利用者の多さやサービスの種類によって、介護職の仕事にちがいがあるんですね。
ですから、その中から自分に合ったサービスを探すことも、介護職を続けていく上では重要です。
たとえば、特別養護老人ホームや、介護老人保健施設では、たくさんの利用者に対して、24時間365日介護を提供します。
特別養護老人ホームでは、寝たきりの方が多くおられ、ベッドから車椅子、車椅子からトイレなど、身体を抱えて移す介護も頻繁にあります。
つまり、身体的な負担が大きくなるんですね。
また、勤務形態も、時間が不規則で夜勤もあります。
いっぽうで、在宅サービスでは、利用者が比較的お元気であったり、夜勤がなかったりします。
施設よりも在宅サービスの方が仕事が楽、という話しではありませんが、身体的な負担にしぼると負担は少ないと言えます。
もちろん、負担によって給料の増減はありますが、自分がなにを重視するかによって、選べるということですね。
自分に合った職場を選ぶことができれば、長く続けられる大きな要因になります。
人材派遣で自分に合った職場を探す
自分に合った職場を探すにあたって、人材派遣会社に登録して、派遣職員として働くという選択肢があります。
派遣で働くことで、直接雇用されるよりも、短期的にいろいろな職場を経験できるメリットがあるからです。
百聞は一見にしかずという言葉があります。
いろいろ調べて、人の話しを聞くことも大切ですが、実際に働いてみないとわからないことも多いです。
不安な人は、派遣で実際に働いてみてから、長期間腰を据えて働く職場を選んでもいいでしょう。
介護職が長く続く人の特徴や長く続けるために必要なこと:まとめ

「急がば回れ、という言葉もありますが、自分に合った職場を選ぶにあたって、人材派遣の活用は良さそうですね 。実際に見ないとわからないことって多そうだし、人から聞いても、それが自分に当てはまるかどうかわかりませんしね」
「そうですね。以前よりもずっと人材派遣で働きやすくなっています。メリットの多い働き方になってきているので、選択肢のひとつとしていいのではないでしょうか」

この記事のまとめ
- 長く続けるためには、うまく人間関係を構築し、相談できる相手を見つけることがポイント
- また、日々の仕事の中でストレスを溜め込まないようにすることも重要。
- ストレスを発散することの他に、そもそも職場でのストレスを減らす努力をする。自分になった職場選びができれば、ストレスも軽減される
- 職場選びのために、人材派遣を利用するのもひとつの選択肢
ということで、今回はこのへんで終わりにしたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。