
「モラルハラスメントってありますよね。たとえば、夫から妻が人格を否定するような発言をされたりってやつです。職場でも起こるって聞いたんですけど、職場のモラルハラスメントってどのようなものを指すのでしょうか。パワハラとモラハラの違いってなんですか?」
「モラハラは職場でも起こりますね。おっしゃる通り、パワハラと共通点があるので、わけるのがむずかしいのですが、モラハラならではの特徴もあります。そのあたりも含めて今回は見ていきましょうか」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護現場におけるモラルハラスメントについて書いています。また、モラルハラスメントとパワーハラスメントの違いについても書いています
こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上携わり、現在は、事業所、施設に対して人材定着のコンサルタントとして活動しています。
さて、介護職が退職する理由のひとつにハラスメントがあります。
パワハラ、セクハラが代表的なものになりますが、モラハラも職場で発生するハラスメントのひとつです。
モラハラは、本人がモラハラをされていると気づかないままに精神がやられていき、加害者の行いが表面化しにくく、解決がしにくい、という特徴あります。
というわけで、今回は介護現場におけるモラルハラスメントについて解説します。
モラルハラスメントとは?

では、モラルハラスメントとは、どういったものなのかについて見ていきましょう。
モラルハラスメントの定義
厚生労働省は、セクハラやパワハラと違い、モラルハラスメントについての定義を明確にしていません。
しかし、一般的な捉え方では「精神的な嫌がらせ、いじめ、相手の尊厳を傷つける発言や言動」となります。
モラハラの特徴をまとめると、次のようになります。
モラハラの特徴
- 精神的なダメージを負うもの
- 本人も周囲も気づきにくい
- 隠蔽される
モラハラは、精神的にダメージを負います。肉体的なダメージはわかりやすいですが、精神的なダメージは直接目で確認できないため、わかりにくいものです。
精神的なダメージは、時に肉体的なダメージ以上に深刻な被害をもたらします。
精神的に破壊されてしまうと、肉体的にも影響が出て、社会生活を行っていくことがむずかしくなるケースが少なくないからです。
周囲に気づかれにくい理由は他にもあって、最初から加害者が隠蔽する意図を持って行っているからです。
加害者は、被害者に対しては精神的にダメージを与えるようなことをしますが、それ以外の人には普通であったり、逆にとても親切であったりします。
ですから、周囲は加害者がモラハラをするような人間と思わないのです。
また、被害者も、モラハラを受けていると認識しにくいという特徴があり、自分がハラスメントを受けているという意識がないまま、精神が蝕まれていく恐れのある厄介なハラスメントと言えます。
パワハラとモラハラの違い
ところで、モラハラの内容を見ると、パワハラとかぶるところがありますよね。
両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
まとめるならば、次のような違いがあると言えます。
パワハラとモラハラの違い
- パワハラには肉体な暴行が含まれるが、モラハラは精神的なもののみとなっている
- パワハラは周囲が気づきやすいが、モラハラは周囲が気づきにくい
パワハラは「優越的な関係を背景とした」という前提になるため、基本上司から部下、先輩から後輩に行われる、と分ける人もいます。
ただし、厚生労働省は「優越的な関係」を上司と部下、といった会社の中でのポジションに限定していません。
能力的に、部下が上司より優越になるケースがあり、それによって起こるものはパワハラとしています。
つまり、部下から上司、後輩から先輩に対するパワハラもある、ということです。
モラハラのひとつであるいじめについても、パワハラの「人間関係の切り離し」と同じと受け取ることができます。
人間関係の切り離しとは、同僚などとの関わりから切り離し、孤立させてしまうことを言います。
自分が気に入らないスタッフがいたときに、他のスタッフを巻き込んでみんなで無視する、などが該当します。
ということは、パワハラの要素の中には、モラハラも含まれ、セクハラにも同様のことが言えます。
重要なことは、どれがパワハラ、セクハラ、モラハラに当たるのか、ではなく、ハラスメントという問題として捉える必要があるということです。
モラハラの加害者、被害者には特徴がある


「ところで、モラハラの加害者、被害者には特徴があるのをご存知ですか?」
「加害者、被害者の特徴?そんなのがあるんですね。その特徴を知っていれば、モラハラをさけることができるかもしれませんね」

モラハラの加害者の特徴
モラハラの加害者には、次ような特徴があるとされています。
加害者の特徴
- 仕事がよくできるように見える
- 攻撃の対象者以外には優しく、常識人のように振る舞う
- 他人に責任を押し付ける
- 言葉がとてもうまい
- 強い者には弱く、弱い者には強い
モラハラの加害者には、仕事がテキパキとでき、そして口が立ち、俗にいう「声の大きい人」である場合が多いです。
良くも悪くも、周囲への影響力を強く持っているタイプですね。
モラハラに至る理由は、根底に、誰かを蔑むことで精神的に満たしたいという欲求があります。
人が困っていたり、悩んでいるのを見ることで、精神が充実するのです。
それに加えて、正義の味方のように振る舞える状況を作ることを得意としています。
被害者を言葉巧みに悪者に仕立てあげ、その悪者に対して制裁を加えているかのような状態を作ることで、周囲の評価を得ていくのです。
その評価を支えているのが、被害者意外には優しく親切、仕事でも他の職員の負担を減らしている、そして、道徳的にも言うことが立派に聞こえる、などの普段の行動があります。
他にも、弱い者をとことん叩く一方で、強い者には弱く、闘っても劣勢になると感じる相手だと、自分の意見を180度変えてしまえる特徴があります。
つまり、管理職などの上司にはうまく取り入ることができるため、有能な人材と誤った評価を受ける機会が多いのです。
モラハラの被害者の特徴
次に、モラハラの被害者になる人の特徴をまとめます。
被害者の特徴
- できごとに対して「自分が悪いのでは?」と思いやすい
- お人好しで優しく、おっとりした性格
被害者の特徴は、いわゆる「いい人」です。
理不尽なことを言われても、それに対して怒りを示すとか、反発するということをせずに、逆に「自分が悪かったのかな」と反省したり、罪悪感を感じてしまう人です。
仕事ができる、できないは置いておいて、テキパキと仕事をこなしていくタイプではない人が被害者になりやすいですね。
介護の現場においては、そういう人こそ利用者に寄り添い、良い介護ができる場面も少なくないのですが、事業所に作業優先の風潮があると、格好の餌食になります。
加害者は、そのような点に周囲を注目させ、まるで被害者の仕事ぶりが他の職員の負担を増やしているかのように指摘します。
そして、自分が改善のために指導しているようにして精神的ダメージを与え、周囲からの賞賛を得るわけです。
モラハラは繰り返される
前述したように、モラハラは隠蔽され、わかりにくいために、問題が表面化することが少ないです。
被害にあった人は、精神的に大きなダメージを負った上に、悪者になって辞めていくケースが多いですね。
被害者が辞めると、加害者は新たな対象者を見つけ、モラハラを繰り返します。
ですから、モラハラをする人がいる職場は、退職者が多く出ることになります。
とはいえ、退職者が出るのは、退職した職員に問題があったから、という結論になるため、ここでもモラハラが問題になることはありません。
つまり、被害者であるいち職員が、自身で解決するのは極めてむずかしいと言えるでしょう。
モラルハラスメントへの対処方法

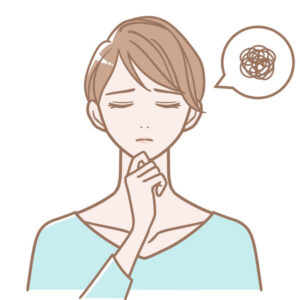
「これじゃあ、モラハラに対処する手がないですよね・・・。改善はできないということなんでしょうか」
「いち職員として働いている場合は、モラハラを改善するのは非常に困難ですね。ですから、加害者から離れる、というのが対処の基本線となります。その前に、まずは自分がモラハラを受けている自覚を持つことが先決ですね」

モラハラにへの対処方法としては、加害者から離れる、ことです。
上司や同僚に相談したところで、わかってもらえない可能性が高く、解決に向けてなんらかのアクションが起こることは少ないです。
ですから、状況を改善させるよりも、加害者と関わらなくて良い環境を作る方法を考えた方がいいでしょう。
具体的には、退職する、異動願いを出す、といった方法です。
そのためには、自分がモラハラを受けているかどうかに気づく必要があります。
気づくためには、自分の精神状態を確認しましょう。
夜眠れない、気持ちの落ち込みが激しい、精神的に不安定、突然涙が出てくる、など、うつのような症状が見られるようなら、精神的にかなりまいっている状態です。
すぐに上司に相談してください。
ここで、上司がモラハラの事実を理解してくれればいいですが、むずかしいようであれば、前述したように退職や異動、もしくは休職の手続きをとるようにしましょう。
自分の精神を守ることを優先してください。
介護現場でのモラハラ、内容や対策を解説します:まとめ
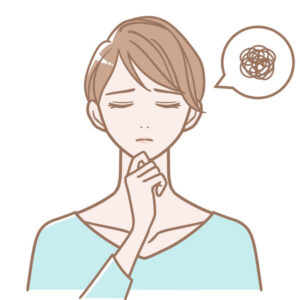
「会社にわかってもらえない、というのはつらいですね。やめるにせよ、異動するにせよ、気持ちをわかってもらいたい、というのも人としてありますよね」
「そうですよね。でも、その点がモラハラではなかなかむずかしいのが厄介ですね。ここは割り切って、自分の身を守ることを優先してください。いずれ、上司も気づく日がくることを祈りましょう」

-

【介護職】パワハラ上司や先輩に悩まされた場合の対処方法
こんな疑問を解決します こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上従事し、複数の施設で施設長を経験しています。現在は、介護コンサルタントとして主に離職防止のノウハウを事業所や施設を回って提供していま ...
続きを見る
この記事のまとめ
- モラハラは精神的にダメージを与える行為
- 隠蔽するため、周囲が気付きにくい
- 加害者、被害者に特徴がある
- 被害者が辞めると、新たな被害者を作り繰り返される
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

