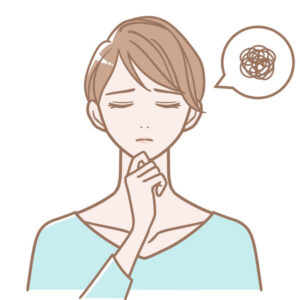
「私、介護職向いていないように思うんですよね・・・。もう辞めた方がいいのかな、なんて考えているんです」
「そうなんですね。介護職に向いている、向いていないって、どんな要素があるのでしょう?。もしかしたら、あなたの悩みは向き不向きの問題ではないかもしれませんよ?まずは、向いていない人の特徴を知って、本当に向いていないかどうか、確認してみませんか?」

こんな悩みを解決します
この記事の内容
介護職に向いていないと悩む人の特徴について書いています
こんにちは、せいじです。
介護の業界に20年以上携わり、介護職、ケアマネジャー、そして施設長などを経験してきました。
管理職になってからは、主に人材育成を担当、1000人以上のスタッフの育成に携わった経験があります。
そして、現在は介護の研修の講師やコンサルタントの仕事をしています。
さて、せっかく就いた介護職なのに、しばらくしたら「自分には向いていないな」と悩み出す人がいます。
その結果、実際にやめてしまう人もいるんですね。
ですが、実は「向いていないのでは」と思う悩みは、自分が思い込んでいるだけかもしれません。
というのも、向いていないと悩む人には、特徴や悩むタイミングがあるからです。
たとえば、特徴としては、介護に理想を高く持っていたり、メリハリをつけることやコミュニケーションが苦手な人、潔癖症や身体が弱い人です。
また、タイミングとしては、仕事をはじめたすぐ、3ヶ月後、半年後、1年後に節目を感じる人が多いです。
しかし、少し視野を広げるだけで、そしてタイミングを乗り越えていくだけで、介護の仕事を楽しめたり、継続できたりするかもしれません。
というわけで、今回は介護職が向いていないと悩む人の特徴や悩むタイミングについて解説します。
介護職が向いていない?それは本当ですか?

では、介護職が向いていないと悩む人の特徴について見ていきましょう。
まとめると次のようになります。
向いていないと悩む人の特徴
- 介護への理想が強すぎる
- 柔軟性がない
- メリハリをつけられない
- 客観的に考えることができない
- コミュニケーションが苦手
- 潔癖症
- 身体が弱い
それぞれ掘り下げていきます。
介護への理想が強過ぎる
介護の仕事に対して、強過ぎる理想を持っている人は、実際に介護職をやってみて、現実とのギャップに悩む可能性が高いです。
なぜなら、初任者研修などの資格で勉強する内容と、実際の介護現場はちがうからです。
初任者研修では、介護の基本を勉強します。
介護の専門職としての土台を作るためですね。
しかし、実際の現場は、介護に加えてそのほかの業務を総合的に実施していかなければなりません。
たとえば、入浴介助をする前の浴室の準備であったり、施設の掃除、ゴミ出しといった業務をしつつ、利用者に介護を提供していく必要があります。
教室で勉強する内容には含まれないことも入ってくるんですね。
つまり、忙しい現場の中で、介護を提供していかなければならないわけです。
ですから、必ずしも一人一人の利用者にじっくりと時間をかけてかかわれない場面も出てきます。
業務をうまくマネジメントしながら、利用者とのかかわりの時間をできるだけ確保する、そのような環境下において、業務優先に見えてしまうことがあります。
ですが、広い視野で考えると、利用者の生活を守るための一部として、業務も必要なのです。
直接的なかかわりだけでなく、業務と呼ばれる間接的なかかわりも、利用者の支援に必要な一部なのだと受け取れるといいですね。
柔軟性がない
前述しやような、生活に必要な一部、と考えられる柔軟性があれば、現実と理想の差を埋めつつ働くことができるかもしれません。
しかし、勉強した内容に固執し過ぎると、ちがいが受け入れられずに苦しむことになる可能性が高いです。
そして、苦しくなって介護の仕事をやめたいと思うかもしれません。
メリハリをつけられない
ですが、介護の現場は、専門的な介護を提供しつつ、そのほかの業務を行なっていかなければなりません。
メリハリをつけて仕事をすることが必要になるんですね。
この場面は、利用者にしっかりと向き合ってかかわる、でも、ちがう場面では業務をしっかりと進めなければならない、といった感じです。
時には、利用者と話しをする時間を後回しにして、業務を優先せざるを得ないこともあるでしょう。
そこは割り切って、できるだけ早く業務を済ませ、後から利用者とガッツリかかわる時間を設けるといった思考が必要になってくるんですね。
客観的に考えることができない
介護の仕事は、客観的にものごとを捉えることが必要になります。
なぜなら、主観で利用者を捉えてしまうと、まちがった見方になってしまうからです。
また、利用者からの希望やクレーム、職員からの指導についても、自分を客観的に見返す力が必要です。
主観で捉えてしまうと、利用者のクレームや、職員からの指導が、自分への批判に感じるでしょう。
そして、批判に傷つき、心が折れて介護の仕事に向いていないと考えてしまうのです。
この状態では負のループに陥ってしまいます。
客観的に捉え、「相手はなにが言いたいのか?どう改善したらいいのか?」と考える思考が大切になります。
コミュニケーションが苦手
コミュニケーションは、介護の仕事には欠かせないものです。
利用者や介護職とコミュニケーションをはかりながら仕事をする必要があるからです。
そのコミュニケーションが苦手だと、仕事をするのに非常に負担が大きくなるでしょう。
自分は会話が得意ではないから、介護職に向いていない、と思う人もいます。
ただし、コミュニケーション能力の高さと、話し上手は必ずしもイコールではありません。
なぜなら、会話だけがコミュニケーションではないからです。
コミュニケーションは「相互理解」という意味になります。
相手を正しく理解し、そして自分を正しく理解してもらうためのものなのです。
ですから、会話以外も含めて、利用者と互いの理解を深めていければ、問題ないのです。
潔癖症
きれい好きな人は、介護職の業務内容が向いていないと感じるかもしれません。
特に、潔癖症とまで言われるぐらいの人であればなおさらですね。
なぜなら、介護では「おしも」の世話をする必要があるからです。
排泄物を目にしたり、処理したりする場面が頻繁にあるんですね。
そのような事柄に拒絶感を強く感じるのであれば、向いていないと思うかもしれません。
ただ、介護の仕事をつづけていくうちに、排泄物が利用者の体調を把握するための、重要な情報であることがわかってきます。
色や形、匂いなどが、利用者の体調の良し悪しの指標になるんですね。
そのような捉え方ができるようになると、排泄物がただの汚物ではなくなってきます。
そのような見方ができるようになれば、汚ないものという意識が軽減されるかもしれません。
身体が弱い
介護の仕事は、身体的な負担が大きい仕事です。
利用者を抱えたり、運んだりしなければならないからです。
また、冬場などは感染症への対策が必要になります。
自身の感染症予防に努めなければなりません。
なぜなら、自分がインフルエンザやノロウイルスに感染すると、利用者にうつしてしまうことがあるからです。
ですから、体力がないとか、体質が弱いといったことがあると、身体がついていかずに向いていない、と感じるかもしれません。
個人の状態によるので一概には言えませんが、体力は努力次第で強化することが可能です。
介護の仕事をするうちに、必要な体力がついてくるということもあります。
また、体質が弱いという点についても、体力の強化や、食事などによって改善の方法が見つかる可能性もあります。
シフト制による不規則な生活が影響するのであれば、シフトを固定してもらえないか職場に相談するのも一つの方法です。
また、デイサービスなど、シフトが固定されている職場に転職するのもいいでしょう。
介護職に向いていないと思うタイミングは?

ここからは、自分が介護職に向いていないのではないかと思いやすいタイミングについて見ていきましょう。
まとめると、次のようになります。
向いていないと悩むタイミング
- 仕事をはじめてすぐ
- 3ヶ月ごろ
- 6ヶ月ごろ
- 1年後
それぞれ、その理由などについて掘り下げて行きます。
仕事を始めてすぐ
仕事を始めたすぐというのは、多くの人がもっとも苦しい思いをするタイミングになります。
なぜなら、新しい環境に適応しないといけなかったり、仕事を覚えなくてはいけないからです。
介護職では、まずは次のようなことをしなければなりません。
最初にしなければならないこと
- 利用者と人間関係を構築する
- 職員と人間関係を構築する
- 業務を覚える
- 介護の知識、技術を覚える
これらのことを、短期間で実施しなければならず、疲弊しやすい環境になります。
なかなか利用者や職員とコミュニケーションがはかれなかったり、業務が覚えられないと、自信をなくしてしまいがちです。
その結果、自分に介護職が向いていないのではないか、と感じるようになるんですね。
とはいえ、最初からうまく仕事ができる人はいません。
多かれ少なかれ、ほとんどの人がうまくいかずに悩んできたはずです。
ですから、自分だけがうまくできなくて、向いていないと悩む必要はないということです。
3ヶ月ごろ
もっとも苦しいタイミングであるスタート時ですが、それでも乗り切れる場合も少なくありません。
なぜなら、とにかく必死でやるしかない環境だからです。
それが、3ヶ月もすると、徐々に落ち着いてきて周囲が見えるようになってきます。
周囲が見えるようになると、自分を他の人と比較するようになります。
その結果、自分の出来なさ加減を感じて、向いていないと悩むようになるんですね。
不安の中で人と比べると、どうしても自分のほうが劣っているように見えがちです。
しかし、人それぞれ長所、短所があります。
あなたにはあなたのペースが、そしてできている部分があるわけで、他の人と同じような状態に必ずしもなる必要はないのです。
比較せずに、自分ができる範囲のペースで積み上げていきましょう。
6ヶ月ごろ
3ヶ月目もなんとか乗り切ったら、次の山は半年が経過したころになります。
半年という期間は、だいたい一通りの仕事が実施できるようになっているタイミングだからです。
比較して、自分の仕事が一人前レベルになっていないと、向いていないのでは?と感じるようになります。
また、この頃までには、同僚への理解も深まってきます。
その中で、合う、合わないというのがはっきりと見えてきて、関係が悪くなっている人もいるかもしれません。
とはいえ、逆に自分を理解してくれている人もいるはずです。
ですから、理解してくれている人に相談をしながら、自分なりに成長していくための努力をするようにしてください。
1年後
1年が過ぎると、自分より経験の浅い職員も増えているでしょう。
その新人職員と対比して、自分の向き、不向きを感じることがあるかもしれません。
自分より後に入った職員が、自分よりも成長が早いと、自分には向いていないな、と感じてしまいますよね。
これまで書いてきたように、人と比較するのを意識して止めるようにしてください。
繰り返しになりますが、できるようになるペースは人によってちがいます。
ですから、比べる必要はないのです。
また、1年が経過すると、介護の仕事にもある程度慣れてくるでしょう。
慣れから介護の仕事へのやりがいや緊張感を失って、ほかの仕事に転職したいという気持ちが芽生えやすくなります。
自分が介護職をどうして選んだのか、原点に立ち返って考えてみてください。
加えて、介護職として働くメリットに目を向けると、解決するかもしれません。
介護職が向いていない?それは本当ですか?:まとめ

「向き、不向きで悩むよりも、発想の転換というか、上手な考え方をもてばいいってことですね!!」
「その通りですね!ものは考えようとよく言いますものね。うまく乗り越えてもらえたらと思います。」

この記事のまとめ
- 介護への思いが強く、柔軟に考えられない人や、コミュニケーションが苦手、客観的に考えることが苦手、潔癖症、身体が弱いといった特徴のある人は、向いていないかも、と悩みやすい
- 仕事をはじめた直後や、3ヶ月ごとに悩むタイミングがやってくる
- 考え方次第で、悩みを解消することが可能
ということで、今回はこのへんで終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
