
「認知症ケアの考え方として、パーソン・センタード・ケアというものがありますよね。どんな考え方なんですか?これから認知症ケアに携わっていくにあたって、しっかりと勉強しておこうと思って!」
「パーソン・センタード・ケアとは、認知症であっても、ひとりの人として当たり前に接し、その人らしい生活をしてもらえるように支援する、という考え方ですね。トム・キットウッド氏が提唱し、世に広まりました。これからますます認知症の方が増えていきますからね。介護職としては絶対に知っておくべき理念と言えるでしょう。では、詳しく見ていきましょうか」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
認知症ケアの基本理念、パーソン・センタード・ケアについてわかりやすく書いています
こんにちは、せいじです。
介護の仕事を20年以上しており、現在は介護の研修の講師やコンサルタントの仕事をしています。
さて、認知症の方の介護をするにあたって、パーソン・センタード・ケアという考え方があります。
パーソン・センタード・ケアとは、認知症であっても、ひとりの人としてとらえ、当たり前に接する、関わることを言います。
それ以前では、認知症の人は、認知症という病気でなにもわからなくなった人、という捉え方でした。
その考え方を大きく変えたのがパーソン・センタード・ケアです。
というわけで、今回は認知症ケアを大きく変えた、パーソンセンタードケアについて解説します。
【認知症】パーソン・センタード・ケアをわかりやすく解説します
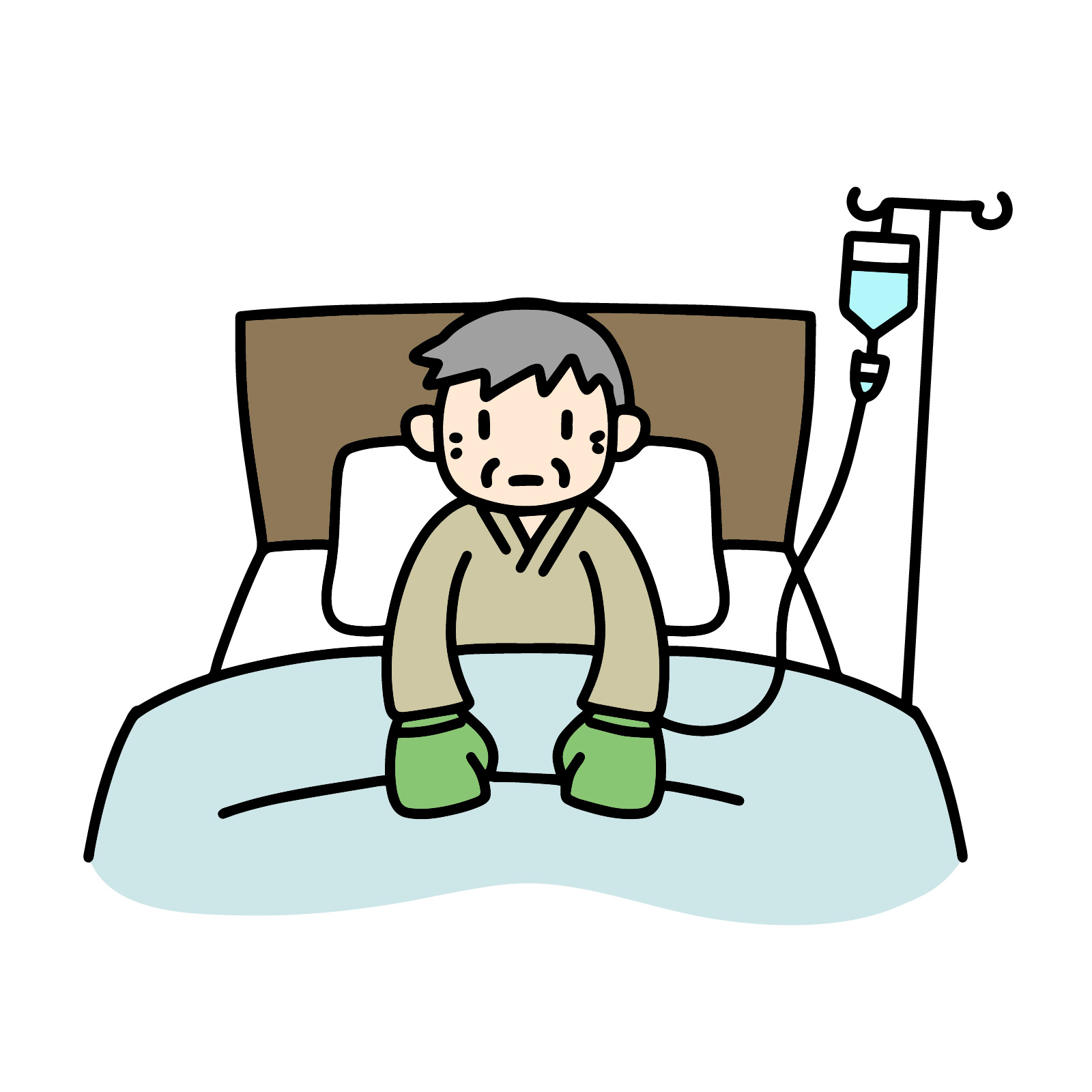
では、認知症ケアの基本姿勢と言ってもいい、パーソン・センタード・ケアについて見ていきましょう。
パーソン・センタード・ケアとは?
パーソン・センタード・ケアとは、イギリスの心理学者、トム・キットウッドが提唱した新しい認知症ケアの考え方です。
たとえ認知症であっても「ひとりの人」として捉え、その人の人生や価値観などを考えながら、その人の立場に立ってケアをすることの重要性を説いたのです。
「トム・キットウッドは、介護福祉士の筆記試験にもたびたび出てくる人物です。パーソン・センタード・ケアセンタードケアと合わせてしっかりと覚えておいてください」

以前の認知症ケア
パーソン・センタード・ケアが広がる前の認知症ケアでは、認知症の方を「なにもわからなくなった人」「なにもできなくなった人」ととらえ、身体介護中心のケアを提供していました。
そして、認知症によって出てくる行動に対して「問題行動」と見なし、時には行動制限をするなどして対応していたのです。
つまり、車椅子などに縛り付ける、ベッドから降りられなくする、といった身体拘束です。
介護の中身は、作業的に三大介護(食事・排泄・入浴)を提供するだけのものでした。
まるで物を扱うように認知症の方に対応していたんですね。
ひとりの人として接するとは?
パーソン・センタード・ケアで求められる認知症への関わりとは、認知症という病気を患っている人、だから、認知症による症状によって、問題行動を起こす人、というとらえ方ではなく、私たちと同じひとりの人間として関わりましょう、というものです。
たとえば、認知症の症状のひとつである徘徊ですが、以前であれば「認知症だから目的なく歩き回る」ととらえていました。
しかし、パーソン・センタード・ケアでは、認知症の方でも目的、理由、原因があって行動を起こすととらえます。
そして、その目的などにアプローチして、認知症の方が穏やかに生活できるように支援していくことが求められます。
つまり、認知症の人の立場や視点に立って理解しようとすることが必要になるんですね。

「出てくる症状への対処ではなくて、そもそもの根本に目を向けようってことですね!」
パーソン・センタード・ケアでの関わり方

ここからは、パーソン・センタード・ケアでの認知症の方への関わり方について、具体的に見ていきましょう。
通常の介護でも同じくですが、認知症ケアでも利用者の全人的理解が必要になります。
全人間的理解とは、身体の状態や病気だけで利用者をとらえるのではなく、その人の心や身体、生活している環境、人間関係など全体的に把握し、生きている世界を理解することです。
全人的理解によりその人の世界を理解する
認知症ケアでは、利用者が生きてきた歴史を知る必要があります。
別の言い方をすると「生活史を知る」という表現になります。
つまり、次のようなことを把握する必要があるのです。
認知症の利用者の理解
- これまでの生活史を知る
- 価値観を知る
- その人の世界を理解する
私たちは、みなそれぞれの世界を生きています。
そして、その世界で、独自の物語を作ってきたのです。
認知症ケアでは、その世界、物語を理解し、その物語に参加する関わりが求められます。
たとえば、徘徊をする利用者の中で、なにが起こっているのか?どのような目的、理由、原因によって歩き回っているのかを考えるのです。
そして、その人の中で起こっている問題が解決できるように関わっていくんですね。
具体的には、トイレに行きたいけれどトイレの場所がわからないで歩き回っているのであれば、トイレまで誘導することで問題が解決します。
食事をすでに食べたのに、食べていない、と訴える人に対しては、「食事を食べていない」世界で関わるのです。
事実は利用者の中にあるわけで、リアルに事実かどうかはどうでもいいのです。
私たちは、利用者の中で起こっている事実に対して、穏やかに過ごすための解決策を提供することが求められるのです。
認知症だから特別ではない
とはいえ、これは認知症の方に対する特別な考え方ではありません。
なぜなら、普段私たちは人間関係の中でごく当たり前にやっているからです。
たとえば「普段は穏やかな性格の人なのに、なぜか今日は機嫌が悪そうだな」と感じることってありますよね。
なにか自分がしたわけでも、そして、リアルになにか起こったわけでもないのに、不機嫌そうなのです。
そのときに私たちはどうするかというと、「なにかあったのかな?体調が悪いのかな?」とその人の立場に立って考えていますよね。
そして、どうしたんですか?なにかあったんですか?と相手に尋ねるでしょう。
話しを聞いて、もし自分が解決策を持っていることであれば、それを提供するはずです。
時には、ただ話しを聞くだけで相手の気持ちが晴れ、解決することもありますよね。
同じことを認知症の方にもするだけなのです。
【認知症】パーソン・センタード・ケアをわかりやすく解説します:まとめ

「認知症ケアを特別なこととしてとらえるのではなく、私たちが普段やっているコミュニケーションと同じことをすればいいんですね。それならできそうですね!」
「基本はそのスタンスで大丈夫です。もちろん、事実と違ったり、混乱されたりすることがあるため、傾聴、受容、共感を含め、いろいろなコミュニケーション技術を駆使していくわけですが、根本は同じです。ぜひ実践してください」

この記事のまとめ
- 認知症の患者を、認知症だから、という目で見るのではなく、私たちと同じひとりの人として接する考え方
- その人の生きている世界を理解し、その人の中で起こっている問題にアプローチすることが必要
- 認知症の患者さんへの関わりは、特別なことをするのではなく、普段の人間関係と同じことをするだけ
認知症の症状についてまとめた記事もあります、下記のリンクからぜひご覧ください。
ということで、今回はこのへんで終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
