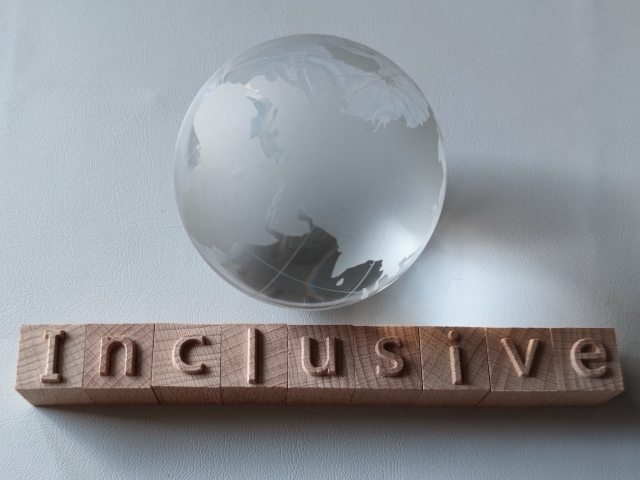「ソーシャルインクルージョンについて教えてください」
「ソーシャルインクルージョンとは、日本語では社会的包摂と呼ばれる考え方です。ノーマライゼーションに似た考え方ですが、違いも含めて見ていきましょう」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
ソーシャルインクルージョンとはなにか?意味や歴史、具体例、また、似た考え方であるノーマライゼーションとの違いについて書いています
こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上携わり、現在は初任者研修や実務者研修などの資格研修や、介護福祉士試験対策講座を担当する講師として活動しています。
さて、介護福祉士試験に比較的出題されやすいものとして、ソーシャル・インクルージョンがあります。
ソーシャル・インクルージョンは、日本語では社会的包摂と訳され「すべての人々を孤独や孤立、排除などから擁護し、社会の構成員として包み、支え合う」ことを理念としています。
「あらゆる人が当たり前に生活できる社会、環境を作る」とするノーマライゼーションの考え方と似ていますが、違いもあります。
というわけで、今回はソーシャル・インクルージョンの考え方、歴史、そしてノーマライゼーションとの違いについて解説します。
ソーシャル・インクルージョンとは?意味などをわかりやすく解説

では、ソーシャル・インクルージョンについて見ていきましょう。
ソーシャルインクルージョンの考え方と歴史
ソーシャル・インクルージョンとは、社会的包摂と訳され「すべての人々を孤独や孤立、排除などから擁護し、社会の構成員として包み、支え合う」を理念とした考え方です。
この考え方は、1970年代のフランスで誕生しました。
たとえば、障がい者や貧困などの少数派のひとたちです。
そのような人たちは「ソーシャル・エクスクルージョン」(社会的排除)と呼ばれるようになりました。
1980年代に入ると、ヨーロッパの各国では財政危機が起こりました。財政危機は雇用の減少を生み、失業者、そして貧困者が増えるといった問題が現れました。
社会は不安定となり、犯罪などが増える中、当時の社会的な考え方は、そのような貧困層を排除する、というものでした。
しかし、問題は解決されないまま、富裕層と貧困層の差が広がるばかりでした。
その中で、ソーシャル・エクスクルージョンが注目を集めるようになったのです。
そして、その対義語として、ソーシャル・インクルージョンという言葉が生まれました。
これまでのように、社会的に排除するのではなく、社会的に包摂しようという考え方、つまり、ソーシャル・インクルージョンの理念として掲げられている「すべての人々を孤独や孤立、排除などから擁護し、社会の構成員として包み、支え合う」社会にしていこうという取り組みがなされるようになりました。
世界的にもソーシャル・インクルージョンの考え方は広まっています。
日本におけるソーシャル・インクルージョンの歴史
日本でのソーシャル・インクルージョンとしては、2006年、「一億総活躍国民会議」に代わるネーミングとして、民間議員の菊池桃子氏がソーシャル・インクルージョンを提案しました。
国は、2025年に向けて、地域包括ケアシステムの構築を謳っていますが、地域包括ケアシステムはソーシャル・インクルージョンの影響を大きく受けています。
ソーシャル・インクルージョンとノーマライゼーションの違い


「ソーシャル・インクルージョンとノーマライゼーションの理念って似ていますよね。違いってあるんですか?」
「ソーシャル・インクルージョンとノーマライゼーションでは、スタート時点の対象者が異なりました。障がい者を中心としているノーマライゼーションと、あらゆる人を対象にしているソーシャル・インクルージョン、ソーシャル・インクルージョンはノーマライゼーションをさらに発展させた考え方と言えるでしょう」

ノーマライゼーションとソーシャル・インクルージョンの違いについてまとめておきます。
| ノーマライゼーション | インクルージョン | |
|---|---|---|
| 対象者 | 障がい者 | 障がい者、高齢者、ひきこもり、外国籍の人などすべての人 |
| 支援 | ほぼ配慮なし | 個別ニーズへの支援を保障 |
| 共生の考え | 障害のある人が障害のない人と時間や場所を共有することを目指す | それぞれの人に居場所があり(地位)、必要とされてそれに応える(役割)こと、同じ市民として支え合い(関係性)を重視 |
ノーマライゼーションは、知的障がい者の生活を問題視したところから始まりました。そして、考えの根底には、障害があっても当たり前に生活できるように、と障がい者が障害のない人と同等に生活できる社会を目指す、というものがあります。
一方で、ソーシャル・インクルージョンでは、障がい者だけでなく、すべての人にそれぞれの独自性、多様性があり、それらが守られるべき、という考え方です。
このような違いから、ソーシャル・インクルージョンは、ノーマライゼーションをさらに発展させた考え方として捉えられています。
【介護福祉士】ソーシャル・インクルージョンとは?わかりやすく解説:まとめ

「ソーシャル・インクルージョンは、ノーマライゼーションの発展系で、障がい者だけでなくすべての人を対象にしている、ということですね」
「そうですね。違いの理解が難しいところがありますが、そのような分け方でいいでしょう。ソーシャル・インクルージョンの勉強ついでに、ノーマライゼーションについても学んでおいてくださいね」

-

【介護福祉士】ノーマライゼーションの覚え方
こんな疑問を解決します こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上携わり、現在は初任者研修や実務者研修、介護福祉士の試験対策講座などを担当しています。 さて、介護福祉士試験に比較的よく出る問題として ...
続きを見る
この記事のまとめ
- ソーシャル・インクルージョンはフランス発
- ノーマライゼーションでは障がい者に重きが置かれているのに対して、ソーシャル・インクルージョンはすべての人を対象にしている
- ソーシャル・インクルージョンはノーマライゼーションの発展系とされる
ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。