
「介護福祉士試験って125問も出題されるんですよね。問題多くないですか!?全部時間内に解答できるかなぁ・・・」
「試験の時間配分は大切ですね。解答して、見直しをして、というところまで時間内におさめる必要がありますからね。そのためにはどれぐらいの時間配分で問題を解いていかなければならないのかを把握しておきましょう」

こんな疑問を解決します
この記事の内容
介護福祉士試験での時間配分について書いています
こんにちは、せいじです。介護業界に20年以上携わっており、現在は独立して介護関係の講師をしています。そして、介護福祉士試験の対策講座を複数の学校で担当しています。
さて、介護福祉士試験は125問からなります。なかなか問題が多いな、時間内にすべて解答できるんだろうか、と感じる人もいるかもしれません。
しかし、実際に試験を受けてみると、普通に進めていければ1度見直しをしてもなお時間が余るぐらいの余裕があります。
とはいえ、どれぐらいのペースで試験を進めていけばいいのかを把握しておくことで心のゆとりが生まれます。
わからない、というのは不安の元ですからね。
というわけで、今回は介護福祉士試験の時間配分について解説します。
介護福祉士試験での時間配分について
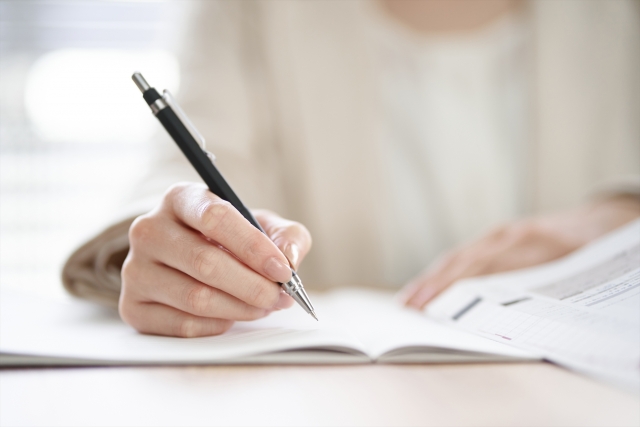
では、介護福祉士試験の時間配分について見ていきましょう。
出題数と試験時間
介護福祉士試験はトータルで220分、125問の出題となっています。しかし、一気に全部するのではなく、午前と午後に分かれて行われるんですね。
詳細を表にまとめます。
| 時間 | 科目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 午前 10時00分 〜 11時50分 (110分間) | 人間の尊厳と自立 人間関係とコミュニケーション 社会の理解 介護の基本 コミュニケーション技術 生活支援技術 介護家庭 | 68問 |
| 午後 13時45分 〜 15時35分 (110分間) | 発達と老化の理解 認知症の理解 障害の理解 こころとからだのしくみ 医療的ケア 総合問題 | 57問 |
ご覧いただくとわかるように、午後より午前の方が11問多くなっています。ですから、午前と午後で1問にかけられる時間が変わってくることになります。
(外国人の場合は、上記の時間の1.5倍になります)
1問につき約100秒ペース
具体的に、午前と午後、それぞれで1問あたりにかけられる時間をまとめると次のようになります。
1問あたりの時間
- 午前:97秒
- 午後:115秒
総合すると、1問あたり約100秒ペースで答えていく必要があるということになります。さらに、見直しの時間として各20分ほどを見積もったとすると、1問約80秒のペースで答えていく必要があることになります。
うまく解けば時間には余裕ができる
1問につ80秒、このわずかな時間で問題文を読んで解答することができるのかな・・・と不安になるかもしれません、
でも、実際にやってみると、多くの人はそれほど時間に困ることはないでしょう。きちんと時間を使えば、意外と余裕を持って解答できるはずです。
では、どのように時間を使えばいいのでしょうか。詳細は次章で取り上げます。
介護福祉士試験で効率よく解答する方法

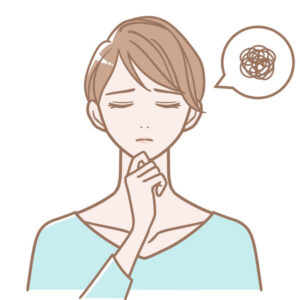
「1問につき80秒って、かなり忙しくないですか。大急ぎで問題を解いていかないと、とてもじゃないけど間に合わないように思おうんですけど・・・」
「たしかに数字だけで見るとかなり短く感じるかもしれませんね。でも、むだに時間を浪費しなければ、時間は余るぐらいだと思います。その無駄な時間の浪費を防ぐ方法について見ていきましょう」

効率よく解答するために
- 濃いめの鉛筆を使う
- 迷う問題は後回しにする
- わからない問題も必ず答える
濃いめの鉛筆を使う
介護福祉士試験はマークシート式で実施されます。選択する白抜き数字を鉛筆かシャープペンシルで塗りつぶすのです。
使う鉛筆やシャープペンシルの芯は、HBやBといった濃いめのものを選んでください。そのほうが短時間でマークすることができるからです。
マークの効率性が上がると、その分時間を短縮することができます。仮に1問につき10秒短縮できれば、全体で20分以上もの時間を浮かすことができます。
また、マークの負担の軽減は、肉体的、精神的な負担を軽減することにもなり、その分問題を解くことに集中できるようになります。
迷う問題は後回し
もし答えに迷う問題に当たったら、いったん後回しにして次の問題に移りましょう。考え込んで時間を浪費してしまうと、その後の問題を考える時間が減ってしまうからです。
答えに悩む問題に時間を割き、悩まなくても正解できる問題にたどりつかなかったらもったいないですよね。
ですから、わかる問題からどんどん解いていく方がいいのです。
そして、すべて解き終わった後、迷った問題に戻ってください。そうすることで、点数の取りこぼしを防ぐことができます。
わからない問題も必ず答える
わからない問題は後回しにすると言いましたが、解答は必ず全問に入れるようにしてください。なぜなら、選択しなければ確実に0点になってしまうからです。
介護福祉士の試験は5者択一式となります。5つの選択肢の中から正解と思う1つ選ぶのです。仮に、当てずっぽうで選択したとしても、5分の1の確率で正解の可能性があります。
しかし、選択しないと100%不正解です。ですから、くれぐれも無回答の問題がないようにしてください。
選択しないと確実にその問題は0点ですが、解答を入れていれば点数が取れる可能性があります。
無回答の問題がないようにしてください。
介護福祉士試験での時間配分について:まとめ

「試験の全体像が見えてくると、余裕を持って問題に取り組めますね。正解率も上がりそうです!」
「そうですね。先に全体像をつかんでおくと、不安は減っていきます。人間、不安にはどうしても気持ちを持っていかれますからね。解消しておくことで試験に集中しやすくなりますね」

この記事のまとめ
- 20分の見直し時間も含めると、1問あたりの時間は約80秒
- 効率よく答えていくために工夫が必要。
- 濃いめの芯を使う、わかる問題から解いていく、でも必ずすべての回答を埋める
過去問を解いていくと、だいたい自分がどれぐらいで問題を解いていけるかが把握できるはずです。
それでも不安な方は、模擬試験を活用して解答ペースをつかんでおきましょう。
そうすれば、試験本番で慌てなくてすみますからね。
というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
